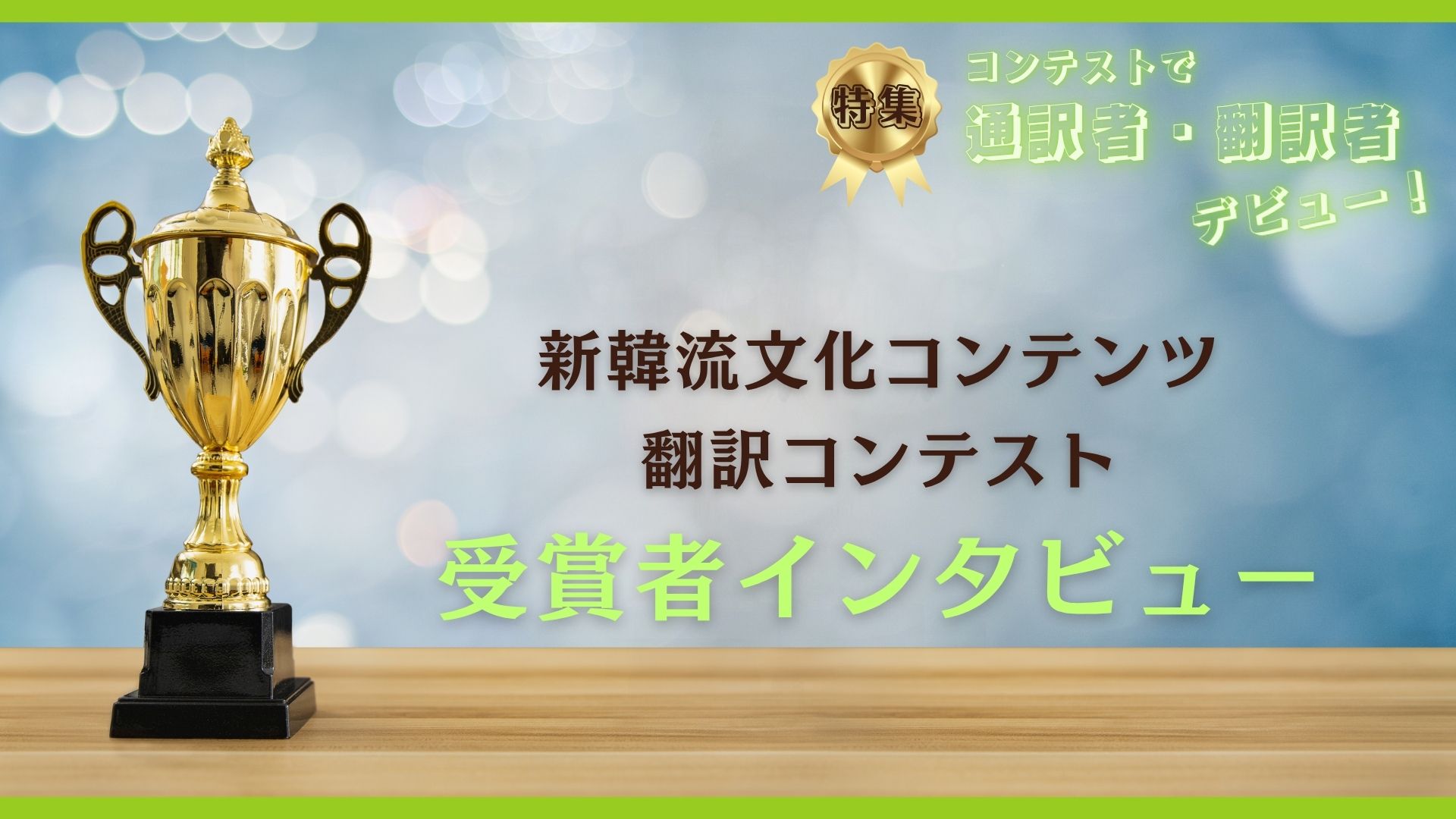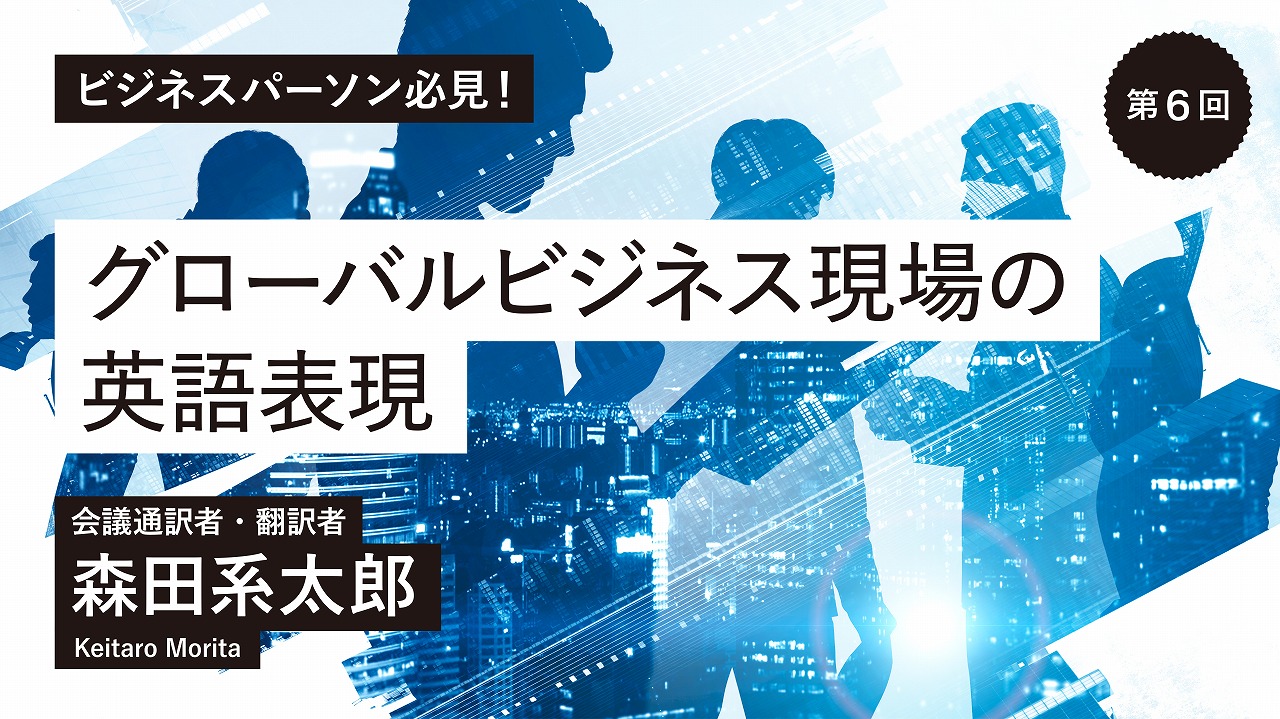2024.01.09 UP
出版翻訳家・ゲーム翻訳家 武藤陽生さん
~Interview with a Professional~

デジタルなゲームの世界と、活字が連なる本の世界。どちらも翻訳者の活躍の場だが、両方を手がける人は珍しい。その境界を武藤陽生さんは苦もなく超えてみせる。
“得意”を実感できるから訳していて気分がいい
それがゲームであれ、本であれ
「訳者略歴 英米文学・ゲーム翻訳家」北アイルランドを舞台にした警察小説〈ショーン・ダフィ〉シリーズの奥付には、そう記されている。1作目の『コールド・コールド・グラウンド』(早川書房)が発売された2018年4月、裏表紙を開いてこの文字列を目にしたときには、胸にこみ上げるものがあったという。
「今でこそプロゲーマーが出てきて、世間の認識もちょっとずつ変わってきていますが、昔はゲームといったら、本より一段低いものに見られていました。それを思うと、『英米文学』と『ゲーム』が横並びになっているのがうれしかった」
13年にフリーランスの翻訳者となって以来、ゲームと出版、2つのジャンルを手がけている。世界的な人気を誇るインディーゲーム『VA-11 Hall-A』(ヴァルハラ)の翻訳者として、ゲーム界隈では知る人ぞ知る存在。また、〈ショーン・ダフィ〉シリーズにおける味のある翻訳は、ハードボイルドの新たな名手誕生を思わせる。「器用さ」だけではとらえ切れない、稀有な才能だ。
学校で出版翻訳を学び
現場でゲーム翻訳を習得
大学時代は、授業そっちのけでゲームにのめり込む一方、現代アメリカ人作家を好む文学青年だった。進路に悩み、「翻訳」という選択肢も頭をよぎったが、現実味のない憧れでしかなかった。結局、卒業後も在学時のアルバイトを続け、人生の展望が見えないまま、時間だけが過ぎていった。
「あの頃はゲームを恨んでいました。高校と大学の大事な時間を、ほとんどゲームに費やしてしまったから。もちろんゲームに罪はなくて、悪いのは自分なんですが」
だが30歳目前のあるとき、バックパッカーのバイブル『深夜特急』(沢木耕太郎 著/新潮社)を読み、スイッチが入った。集中的に英語を学び直し、人生初の海外へ。本と同じルートで、インドから陸路でギリシャ・アテネに向かった。行く先々で英語の通じる現地人と言葉を交わすと、何の因果か、その多くは翻訳者。頭の片隅に埋もれていた「憧れ」が息を吹き返し、3カ月半の旅を終える頃には、覚悟を決めていた。
「やりたいことに挑戦するなら、年齢的にこれが最後だろうと。帰国してすぐ、翻訳学校に通い始めました」
文芸翻訳をやりたいと、フェロー・アカデミーの那波かおり氏、川副智子氏のクラスを経て、田口俊樹氏に師事。その傍ら、学校の母体が運営する翻訳情報サイトを介してゲーム翻訳の求人に応募し、週に5日、ゲーム関連会社で社内翻訳者として働いた。
「当時はもうゲームに何のわだかまりもなかったし、“洋ゲー”ならさんざんプレイしてきましたから、単純におもしろそうだなと。じつは入学するまで、『ゲーム翻訳』という仕事が存在するとは知らなかったんです。その会社には4年ほど勤めましたが、ローカライズの工程をいろいろ学び、フリーランスとして独立する足がかりになったので、経験として大きかったですね」
文芸翻訳のほうは、田口氏のクラスに入るやいなや、壁にぶつかった。その指導は「とりあえず、プロとして食えている私のやり方を真似てみなさい」というスタイル。だが、つい自分流を貫いてしまい、なかなか評価されなかった。転機は、『エリア51世界でもっとも有名な秘密基地の真実』(太田出版)の下訳チームに選ばれたとき。起死回生を狙い、他のメンバーへのフィードバックを完璧に消化すると、師になりきって自分の担当箇所を訳した。
「赤字がわずか1箇所で、初めて田口先生に褒められました(笑)。仕事を振ってもらえるようになりましたし、何より認めてもらえたのがうれしかったです」


※『通訳者・翻訳者になる本2022』より転載 取材/金田修宏 撮影/合田昌史 取材協力/フェロー・アカデミー
Next→師の教えを守り、破って
自分流が見つかった

早稲田大学法学部卒。アルバイトを経て、ゲーム翻訳会社に勤めながらフェロー・アカデミーで文芸翻訳を学び、2013年にフリーランスの翻訳者に。主な訳書に『コールド・コールド・グラウンド』『アイル・ビー・ゴーン』(以上、早川書房)、『DX実行戦略 デジタルで稼ぐ組織をつくる』(日本経済新聞出版)『ゲームライフ――ぼくは黎明期のゲームに大事なことを教わった』(みすず書房)など。主な翻訳ゲーム作品に『VA-11 Hall-A』(Sukeban Games)『Gone Home』(The Fullbright Company)など。