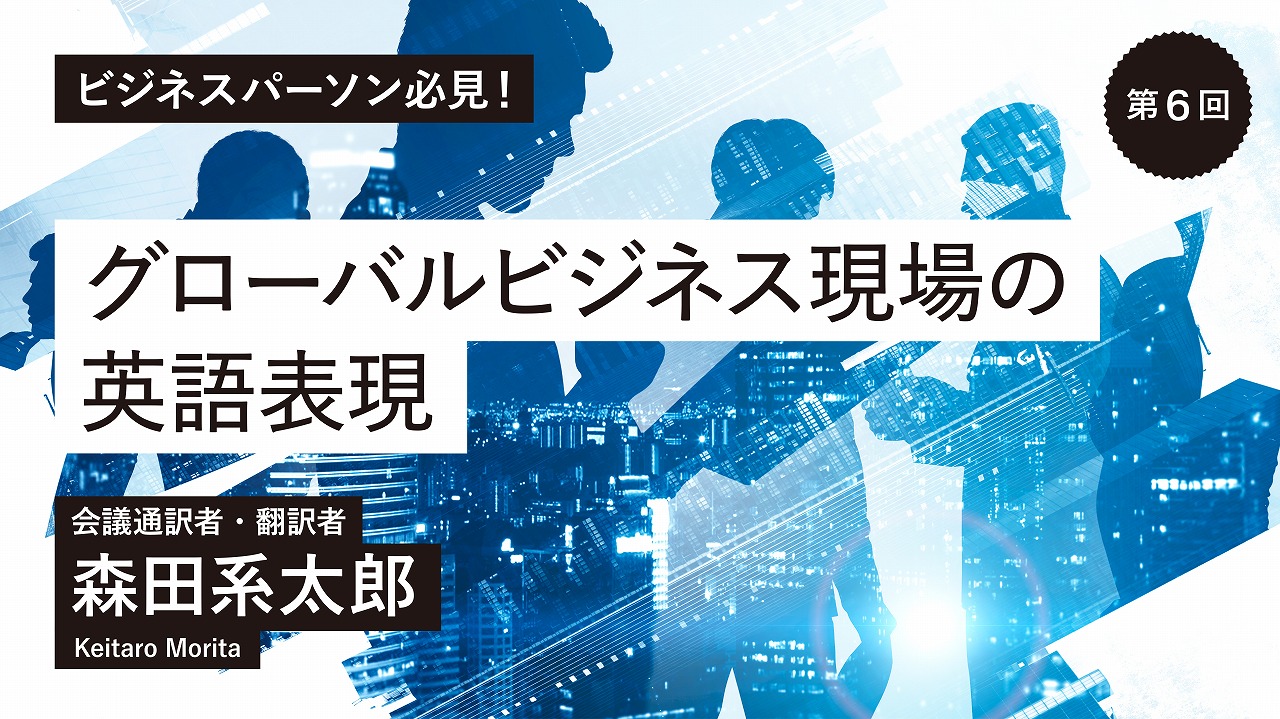Contents
アメリカ文学の研究者である、立教大学文学部 教授の舌津智之先生が、英語圏の小説や映画、曲のタイトルや、多くの人が一度は聞いたことがある名台詞・名フレーズの日本語訳に見られる独創的な「誤訳」に着目して、その魅力を解説します!
古典的なアメリカ映画に見られるタイトルの「誤訳」
誤訳がしっくりくる日本人の感覚
近年、洋画や洋楽の作品タイトルは、そのままカタカナにしておけばよい、という慣例がすっかり定着したようである。が、たとえば、『アベンジャーズ』や『マレフィセント』という題名が持つ英語本来の意味をいったいどれだけの日本人が理解しているのだろうか?
洋楽の場合はタイトルをカタカナにすることすらしばしば回避されるようになり、K-POPの英語の曲名などは日本でもアルファベット表記のまま紹介されている。
そもそも最近の若いリスナーは、サウンドや動画のノリで音楽を楽しんでいて、歌詞や曲名などほとんど気にしていない。
しかし、無理やりにでも横文字のタイトルを縦に直していた時代には、誤解や工夫や偶然が重なって、時に独創的な邦題が考案されていた。本連載では、タイトルの「誤訳」によって独自の意味づけがなされ、結果としてそれが「名訳」になるという、創造的な翻訳の実例をいくつか見ていくことにしたい。
今回はまず、古典的なアメリカ映画の邦題にスポットを当てる。
翻訳が明かすPhantomの正体
『オペラ座の怪人』
The Phantom of the Opera(1925年)
本作品は今日、ミュージカル作品として名高いが、当初は『オペラの怪人』という邦題で、戦前から何度も映画化されている。
ただし、「怪人」という日本語は誤訳である。原題の“phantom”は、「幽霊」や「化け物」や「幻」であって、人間ではない。実際、1930年に出た原作の邦訳(田中早苗訳)は、『オペラ座の怪』と題されており、こちらは忠実な直訳である(「怪」=「化け物、変化(へんげ)」)。「怪人」と訳したら、いかに謎の存在であれ、それが人間だと明かすことになり、ネタバレの邦題となってしまう。
ただ、それでも、「怪人」という「誤訳」が意外にしっくり来るのは、この男が、顔の一部を隠す仮面を被っていることと無縁ではなかろう。というのも、ある年齢以上の日本人ならば、「怪人」といえば「怪人二十面相」を連想し、そのトレードマークであるアイマスクを懐かしく思い出すに違いないからである。

「それ」とは一体なにか!?
『女はそれを我慢できない』
The Girl Can’t Help It(1956年)
英語では、特定の指示対象を欠いたまま、熟語的に“it”を用いることがある。「間に合う、成功する」の意味で使う“make it”などはその典型例だが、“can’t help it”という表現も、「仕方ない、避けられない」と訳すのが普通であり、代名詞の“it”をいちいち「それ」と訳出するのは一種の直訳的誤訳である。
ちなみにリトル・リチャードが歌う『女はそれを我慢できない』のタイトル・ソングは、「通り過ぎる彼女に男たちが夢中になっても/彼女にはどうしようもない(she can’t help it )」という歌詞で始まっている。「彼女はそれを我慢できない」などという意味ではない。そもそも、「我慢できない」なら“can’t stand it”のはずである。
しかし、マリリン・モンローとも比較される女優のジェーン・マンスフィールドが主演するこの映画の邦題は、「それ」に性的な連想を込め、欲望を抑圧しない女性の官能的イメージを呼び覚ますことで、映画のお色気ムードと女性の自由・解放を巧みに演出したのである。
“異常な” 翻訳ゆえの名訳
『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb(1964年)
ウィキペディアでこの映画の項目を見ると、「Strangeloveとは人名であり、忠実に訳すなら『ストレンジラヴ博士』もしくは『ドクター・ストレンジラヴ』となる」との説明がある。その通りである。が、「strange loveを訳すれば『異常な愛情』となる」と書かれているのは嘘だと言わざるをえない。
どんな英和辞典を見ても、“strange”という形容詞に「異常な」という訳語を付してはいないだろう。「奇妙な愛情」「不思議な愛情」ならありえても、「異常な愛情」と訳すのは明らかに行き過ぎである。
にもかかわらず、この邦訳が定着したのは、日本の社会事情がからんでいるのではなかろうか。本作品が公開されたのは、安保闘争の記憶も新しい1964年であったが、被爆国民である日本人は当時、核爆弾を愛するような人物は、「奇妙」や「不思議」では生ぬるく、「異常」であるとみなす良識を持っていた。
言葉は、その背後にある価値観を常に映すものである。2023年のいま、かつてのように核が「異常」であるとは思っていない改憲派の政治家であれば、これを「博士の普通の愛情」と意訳したいところではあるまいか。
★こちらの連載も要チェック!

1964年生まれ。東京大学大学院修士課程、米国テキサス大学オースティン校博士課程修了(Ph.D.)。専門はアメリカ文学、日米大衆文化。主な著書に、『どうにもとまらない歌謡曲―七〇年代のジェンダー』(ちくま文庫、2022年)、『抒情するアメリカ―モダニズム文学の明滅』(研究社、2009年)、共訳書に『しみじみ読むアメリカ文学』(松柏社、2007年)など。