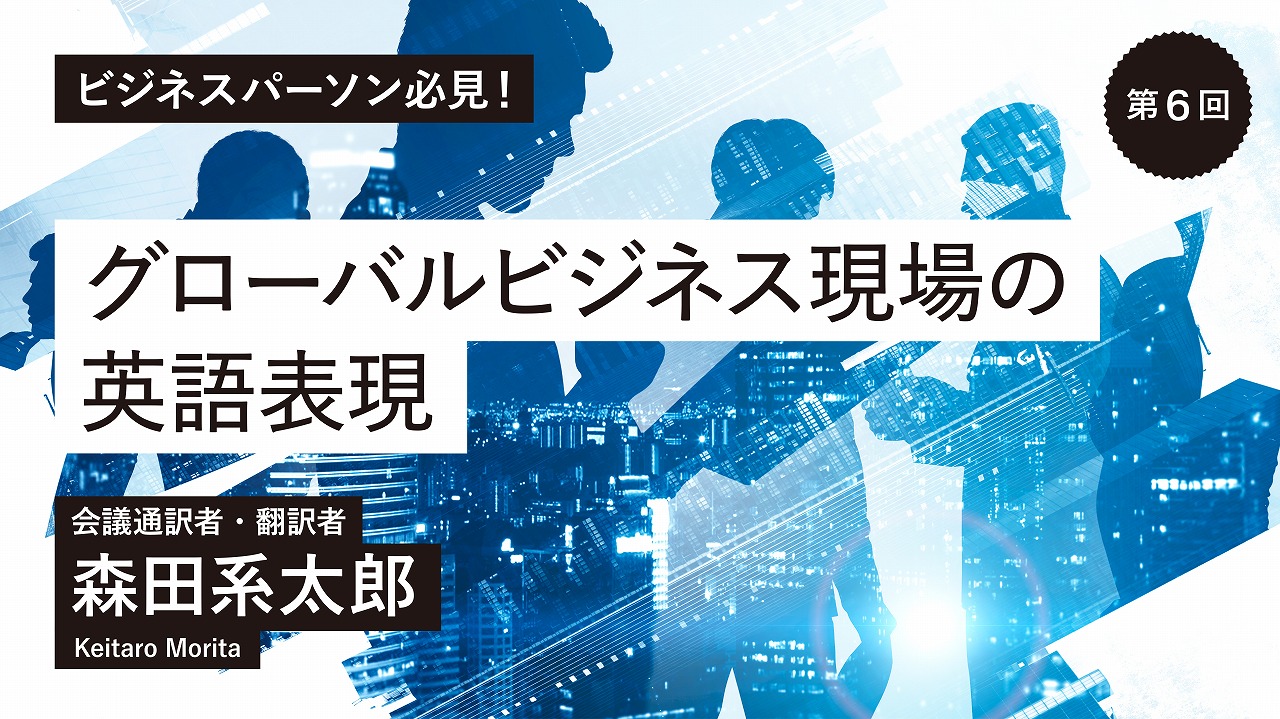Contents
季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
やはり触れないわけにはいかないだろう。本来ならオリンピックを間近に控えていたはずの今(2020年7月半ば時点)、コロナ禍はいっこうに収まる気配がない。普段から部屋にこもりきりで仕事をしているので、実は自粛期間中も基本的な生活パターンはあまり変わらなかった。
しかし、である。なぜか仕事が進まないのだ。心がざわざわして落ち着かず、原文を読んでも集中できずに目が上滑りしていく。心配なニュースばかりが耳に入ってきて、原文の「声」がちっとも聞こえてこない。翻訳というのは、原文を噛みしめ、声に耳を澄ます作業なのだなとつくづく思い知らされる毎日だ。
スペイン語を専攻英語で翻訳を学ぶ
声に耳を澄ます作業というのは実は日本語の文章でも同じで、「意味」はわかっても、著者の「声」は耳を澄まさないと聞こえてこない。子どもの頃から本を読むのが好きで、声を聴くことには少しは慣れていたのかもしれない。大学ではスペイン語を専攻した。そこでスペイン語の短編を読んで内容を把握するという授業があった。それが思いのほか楽しかったのだ。まさに声を聴く作業だったような気がする。
翻訳という職業を意識したのは、大学卒業後に勤めていた会社が関西へ移転することになったこともあったが、この大学のときの体験が影響したように思う。でもスペイン語で翻訳など思いつきもせず、翻訳学校で英語の文芸翻訳を学び始め、何人かの先生に教わったのだが、中田耕治先生との出会いが大きかった。それまでは横のものを縦にするのにただ必死だった。「君たちが訳した本は、村上春樹の横に並べられるかもしれない。それでも選んでもらわなきゃならないんだ」と言われ、初めて「仕事としての翻訳」の何たるかに思い当たり、背筋が伸びた。わたしたちは、訳したものを読者に読んでもらわなければならないのだ。
翻訳学校で親しくなったクラスメートのつてで、ある翻訳家の下訳などをさせてもらううちに、その方の紹介で初めて自分の名前で翻訳書を出すことができた。洋楽に多少なりとも関心がある人に、と依頼されたその仕事は、パンク・バンドの代表格とも言えるセックス・ピストルズのムック本だった。奥付を見ると1996年なので、もう20年以上前のことだ。翻訳の勉強を始めて3、4年は経っていただろうか。ピストルズにことさら詳しいわけではなかったし、当時はインターネットなどないも同然だったので、調べ物はそれなりに大変だったが、本を探したり、CDを買い漁ったりするのはむしろわくわくした。よく言われることだけれど、調べ物が苦にならない人、何にでも興味が持てる人は、たぶん翻訳者に向いている。
スペイン語の翻訳の仕事もスタート
その後、二人の子どもの子育てをしながら細々と英語の翻訳を続けていたが、あるときスペイン語のリーダーを探していると声をかけていただいたのがきっかけで、再びスペイン語と関わるようになった。大学以来だったのですっかり錆びついていたけれど、月に一冊ぐらいずつ原書を読み、勉強させてもらった。
そうして出た初のスペイン語の訳書は、スペイン統一を成し遂げたイサベル女王の娘の伝記『女王フアナ』(角川文庫)。公開される映画の関連書だったから、スケジュールはきつかったが、スペイン語翻訳の第一歩を踏み出すことができて嬉しかった。
現在も英語とスペイン語の二足の草鞋を履いている。翻訳する割合は英語が7割、スペイン語が3割ぐらいだろうか。スペイン語の出版翻訳者はとても少ないが、日本で翻訳される書籍の数も英語に比べれば微々たるものだ。依頼もそうそうないので、持ち込みで出版にこぎつけたケースが少なくない。大きく変動する世界情勢のなか、今後は各国の出版業界や市場の声にもさらに耳を澄ます必要があるだろう。
※ 『通訳翻訳ジャーナル』2020年秋号より転載

スペイン語・英語翻訳者。東京外国語大学スペイン語学科卒。外資系企業勤務後、翻訳者に。『舌を抜かれる女たち』(メアリー・ビアード著、晶文社)、『幻覚剤は役に立つのか』(マイケル・ポーラン著、亜紀書房)、『羊飼い猫の日記』(スザンナ・クランプトン著、ハーパーコリンズ・ジャパン)など訳書多数。
*『通訳翻訳ジャーナル』2020年秋号・掲載当時*