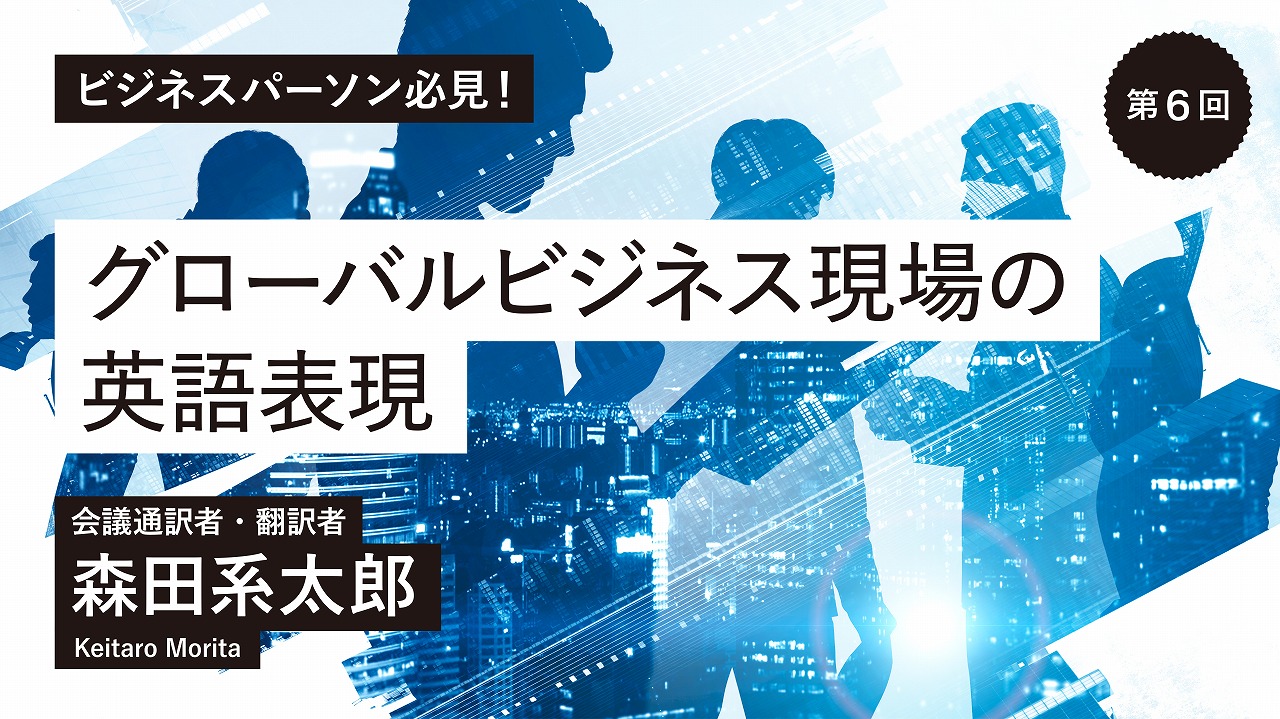季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
幼い頃から本を読むことや文章を書くことが好きだったわたしは、小説家への憧れをずっと抱いていた。しかし、ゼロから物語を生み出す能力がないことをほどなく思い知らされ、作家への道は断念することになった。いったい自分にはなにができるのだろうと考え、子どもの頃から好きだったことを頭のなかで並べてみた。読書、外国語、文章を書くこと、深く考えること、ひとりでいること、じっと座っていること。そのすべてを混ぜ合わせてみると、「翻訳」という仕事が思い浮かんだ。外国の小説を自分の言葉で日本語に移しかえていくのは、ゼロからなにかを生み出すのではないにせよ、ほとんど創作に近い作業だといえるのではないか。これはもしかしたら自分に向いているかもしれない。そうして翻訳学校に通いはじめたのは、20代終わりの頃だった。
翻訳学校(フェロー・アカデミー)では全日制の総合コースに一年通ってさまざまな種類の翻訳を経験し、その後、文芸作品やミステリー小説を題材にした東江一紀先生のゼミに3年ほど通った。わたしはもともと内向的でひねくれ者でもあったため、教員からかわいがられるタイプではまったくない。しかし、先生いわく「翻訳はむしろそういう人のほうが向いているし、喋るのが得意なら、翻訳でなくても生きていけます」。さいわい翻訳学校では訳文がすべてだ。熱意をもって授業に臨み、全力で訳文を仕上げて提出していれば、どんなに目立たない生徒でも、その努力を先生は必ず見ていてくれる。
勉強会をきっかけにデビューをつかむ
ゼミとは別に、「ニューヨーカー」誌の短編小説を訳す勉強会に参加していたとき、ゲストで来ていたハーレクインの編集者から声をかけていただいた。ロマンス小説を10冊ほど翻訳したあと、東江先生の紹介で、『分類項目: 殺人』(福武書店)というミステリー小説でデビューすることができた。そのあとも、先生の家で開かれる勉強会で、仲間と切磋琢磨しながら翻訳のテクニックを磨いていった。
英文をていねいに読んで解釈し、それを自分の言葉で日本語に落とし込んでいく作業はわくわくするほど楽しかった。勉強会で先生に教えられたことは数知れないが、もっとも胸に響いたのは「自分が読みたいと思える文章を書きなさい」という言葉だ。翻訳をしていると、どうしても原文に引きずられてしまい、「原文にはこう書いてありましたので」と言いわけしたくなる。しかし、それは読者にとって読みやすい文章とはいえない。そんなときは訳文を見直しながら、「これはわたしが読みたい文章だろうか?」と自問するようにしている。
一時期、翻訳から離れ第二のデビュー作も
わたしの場合、必ずしもコンスタントに翻訳の仕事を続けてきたわけではなく、途中で哲学の勉強に夢中になって翻訳から離れていた時期もあった。そんなわたしをふたたび翻訳の世界に連れ戻してくれたのも東江先生だった。「おもしろそうな哲学の原書があるので、読んでみないか」とリーディングを託された。読んでみるとすぐに惹き込まれ、読みながらいつのまにか頭のなかで翻訳しはじめていることに気づいた。すぐにでも訳したい、と思えたのは久しぶりのことだった。
ところが、リーディングのレポートを提出した出版社からは、出版を見送るという返答があり、それならしかたがないといったんはあきらめた。しかし時間がたつにつれ、「やはりあの本を翻訳したい」という強い想いが湧いてきて、悩んだ末、思い切って先生に相談した。すると、翻訳エージェントに梗概と試訳を送ってみるよう勧められた。ふだんのわたしならとっくにあきらめていたはずが、なぜかこのときばかりは、なにかに突き動かされるように行動的だった。しばらくしたころ、編集者から連絡があった。そうしてできあがった本が、わたしの第二のデビュー作ともいえる『100の思考実験』(紀伊國屋書店)だ。ありがたいことに、この本は現在も版を重ねている。
これまでさまざまな経験をし、たくさん回り道もしてきたが、結局はすべてが翻訳という仕事に結びついていた。人は天職に行き着き、天職に還るものだと今は思っている。
※ 『通訳翻訳ジャーナル』2022年冬号より転載

翻訳者。早稲田大学第一文学部卒。訳書に『哲学の女王たち』(晶文社)、『プリズン・ブック・クラブ』『アウシュヴィッツの歯科医』(紀伊國屋書店)など。非常勤で中高一貫校の図書館司書として勤務。30 年以上続く読書会にも参加している。