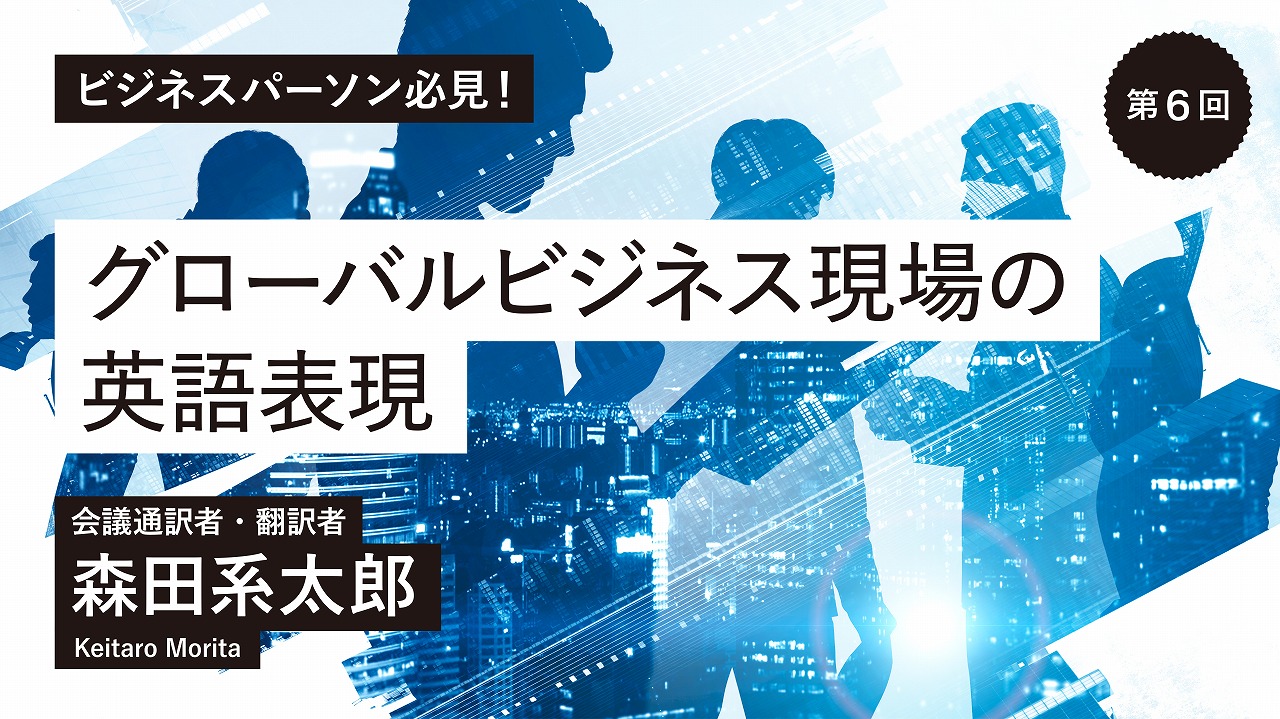Contents
季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
翻訳という仕事を最初に意識したのは中学生の頃でしょうか。初めて習う英語が楽しくてたまらず、「大好きな『赤毛のアン』を英語で読んでみたい!」と原書を手に入れました。もちろん読めるはずもなく、「わたしがアンを日本語で楽しめるのは、この村岡花子さんという人のおかげなのだな」と思ったのを憶えています。
翻訳学習を開始し すぐに会社を退職
次に翻訳を意識したのは社会人になって数年目。仕事帰りに英会話学校に通いだしたのをきっかけに、その昔、翻訳家に憧れたことを思いだしてしまったのです。ちょうど30歳を目前にしていたこともあり、「やらずに後悔より、やって後悔」と翻訳学校の通学コースを受講することにしました。「3年勉強して、ものにならなければあきらめる」と期限を定め、退路を断つために会社も辞めました。なんとも無謀な話です。それでも逃げ道がなくなったことで、もう前に進むしかないと覚悟が決まりました。
幸い、3年の期限が来る前にリーディングや下訳の仕事がぽつぽつと入り始めました。リーディングは版権エージェントからの依頼で、出版社に売り込む原書に添えるレジュメを、多いときで月に3、4本書いていました。
デビュー作となる『聖女伝説エビータ』は、そのリーダー時代にお世話になった方からの依頼でした。アルゼンチンの伝説的なファーストレディ、エバ・ペロンの生涯を描いた映画『エビータ』の公開に合わせて急遽出版が決まったのです。あのマドンナ主演ということでも話題になった映画の関連本をなぜわたしに? 訳文を読んだこともないのに? そう尋ねると、「訳せる人かどうかはレジュメを読めばわかる」と言われました。驚くと同時にうれしくなりました。見ていてくれる人はいるのですね。その後、版元が変わるというトラブルはあったものの、翻訳者として自分の名前が記された本を手にしたときの感動は忘れられません。
デビューを果たすも訳文に悩む
ところが、デビューしてすぐに壁にぶち当たりました。下訳の仕事を長くしていたこともあり、どうしても他人の評価が気になって、試験の答案のようなぎこちない訳文になってしまうのです。そんなときにいただいたのが、性産業で働く女性たちを追ったルポルタージュ『彼女のお仕事』(原題 Working Sex)でした。エスコート・ガール、ポルノ女優、SMの女王、トランスジェンダー。自分らしさを求めて性産業に飛び込んだ彼女たちの「声」はじつに生き生きとして、正しいだけの訳文には到底収まりません。
多少のアレンジを加えたほうが断然おもしろくなるけれど、意訳しすぎだと批判されるだろうか? ぐるぐると考えているうちに頭のなかでぷつんとなにかが切れました。自分の訳したいように訳そう。それで批判を受けるならしかたがない。そう吹っ切れてからは訳すのが楽しくなりました。それだけに刊行後、ある週刊誌の書評欄で「訳文のキレがいい」と言ってもらえたときは飛びあがるほどうれしかったです。
翻訳の仕事と並行して、数年前から翻訳学校で通信講座の講師をしています。自分が教える立場になるとは思いもしませんでしたが、学ぶ側としての経験は豊富なので、そこからなにか伝えられればと思っています。最初の講義でかならずお話するのは「翻訳は意外に自由だ」ということ。もちろん原文という「縛り」はありますが、そこからはみださなければどんな日本語表現を選んでもいいわけです。
辞書にない自分だけの訳語を見つける―これこそ翻訳の醍醐味だと思います。使える言葉はないかと、つねに目を見開き、耳をそばだてています。寝入りばなのうとうとしているときに「これだ!」とひらめくこともあるので、枕元にペンとメモを常備しています(朝になって読み返すと、たいてい使えないのですが)。ぴたっとくる表現が浮かんだときは「わたしって天才!」と思うことも。そうした「勘違い」を心の糧にしてパソコンに向かう日々です。
※ 『通訳翻訳ジャーナル』2021年夏号より転載

英米文学翻訳家。横浜市立大学国際関係学科卒。主な訳書に『妻に恋した放蕩伯爵』(竹書房)、『アースクエイクバード』(早川書房)など。趣味は観劇(とくに小劇場系)。芝居を観たあと、ビール片手にああでもないこうでもないと感想を言い合える日々が早く戻りますように。