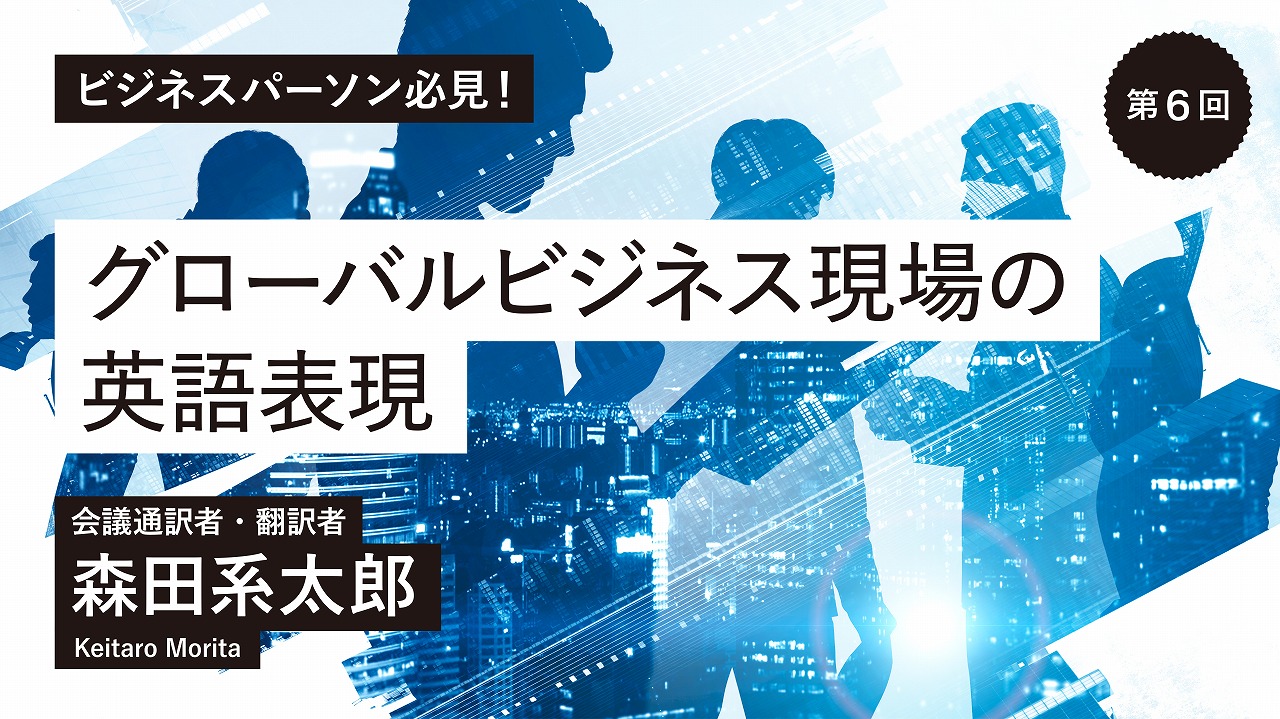季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
気がついてみると、まだ翻訳の道を歩んでいる。初期のつらさ苦しさは、いずれ楽になるになるだろうと思っていたが、べつだん変わりはないようだ。
2、3冊ほど訳書が出た頃、「いかだで太平洋に漕ぎ出してしまった気分です」と、翻訳の大先輩に言っていたのを思い出す。故人となってしまわれたその山岡洋一さんは、貴重な助言や忠告をして下さった。翻訳者は憧れてなるようなものではない。出版翻訳をめざすのは野球少年がプロを夢見るのと変わらない。休日も保障もない、だから病気になることもできない。人づきあいが犠牲になる孤独な作業だ。文章を書くという狂状態が続くし、苦労が多いばかりだ、それに何より、本の翻訳で食べていける時代は終わりつつあるんだよ、というようなことを。
長い海外生活を経て翻訳の世界へ
かれこれ20年近くが経った今では、どの忠告も本当だったことがよくわかる。翻訳に引き寄せられたのは、本が好きという、ただそれだけの動機だった。とりたてて語学が好きというわけでもなかった。それでも父の転勤であちこちを転々としていたせいで、スペイン語、ポルトガル語や英語で、いつでも本は読んでいた。日本語の本が手に入らなかった時代のことで、文字を追わずにはいられない活字中毒を満たすためには、そうするしかなかったからだった。バイリンガルだから苦労はいらなかったという図式には、悲しいことに当てはまらないように思う。日本人の家庭で暮らしていれば、そんなにたくさんの言語を自在に操れるものではないし、身についたはずの外国語も、日本に戻れば、銀河の果てに飛び去ってしまうのだから。しばらく日本を離れていると、日本語すらおかしくなってきてしまう。
ともあれ、そんなカオスめいた言語脳で脳内翻訳をしながら本を読みあさってきたので、北欧に7年ほど滞在して帰国したときに、思い浮かぶ仕事は翻訳しかなかったのだった。情熱に駆られたわけでも夢を抱いていたわけでもなく、山があるならそこに登ろうというだけだった。厳しい忠告は、そんな甘い料簡でやっていけるはずがないと思ってくださった山岡さんの温情だった。当然過ぎるほど当然のお言葉だっただろう。
そうは言っても、イメージできるものが翻訳しかなかったので、まずは英語の学び直しから始めようと思い、少人数の翻訳クラスに通うことにした。毎日通学する2年間のコースだったが、1年目の半ばを過ぎた頃に、やってみないかとそこで紹介された本が、最初の訳書になった。出版翻訳の第一歩がこの『理想なき出版』(柏書房)という、メディア・コングロマリットが跋扈する大波が出版を崩壊させていく内容の本だったのは、何ともアイロニカルなめぐり合わせだったかもしれない。
スペイン語も手がける 翻訳は歩き続ける仕事
幸いにそれからは、ご縁があった編集者から自己啓発系の本を頼まれたり、ぽつりぽつりと他の出版社の仕事に恵まれたりしながら、スペイン語の書籍も手がけるようになり、よろよろと歩くうちに、訳書が40冊を超えていた。作業の苦しさや苦労は、山岡さんの言うとおりだった。けれども翻訳の道に踏み込むほど、その魔力のおかげでしんどさが中和されてきたような気がしている。いつかは楽になる日が来るとも思わなくなった。いかだで大洋に漕ぎ出した気分でいた頃は、何かをめざさなくては、達成しなくてはと思う気持ちがあったものだが、それは間違っていたことにも気がつくことができた。
出版翻訳とは、一字一字を積み重ね、一枚一枚原稿を仕上げていくだけ、ただ歩きつづけるだけの仕事だった。いかだで漂いながら陸地をめざすようなものではなくて、千里の道は、どんなに進んでも終わりのない千里だったのだ。それに気がついてからは、無心で翻訳に向き合えるようになった。どこやらマゾヒスティックな喜びが覚醒したのかもしれない。ちょっぴり寂しいのは、脳内翻訳で自由に本を読む醍醐味が、どっかり居座っている翻訳者の厳密なダメ出しで水をさされてしまうことである。ああ無念。
※ 『通訳・翻訳ジャーナル』2021年冬号より転載

出版翻訳者。獨協大学外国語学部講師。訳書に『ファシズム―警告の書』(みすず書房)、『天使のいる廃墟』(東京創元社)、『ユー・アー・ヒア あなたの住む「地球」の科学」(早川書房)、『悪女』(創元推理文庫)、『深い穴に落ちてしまった』(東京創元社)、『バサジャウンの影』(ハヤカワ・ミステリ)など。
*『通訳翻訳ジャーナル』2021年冬号・掲載当時*