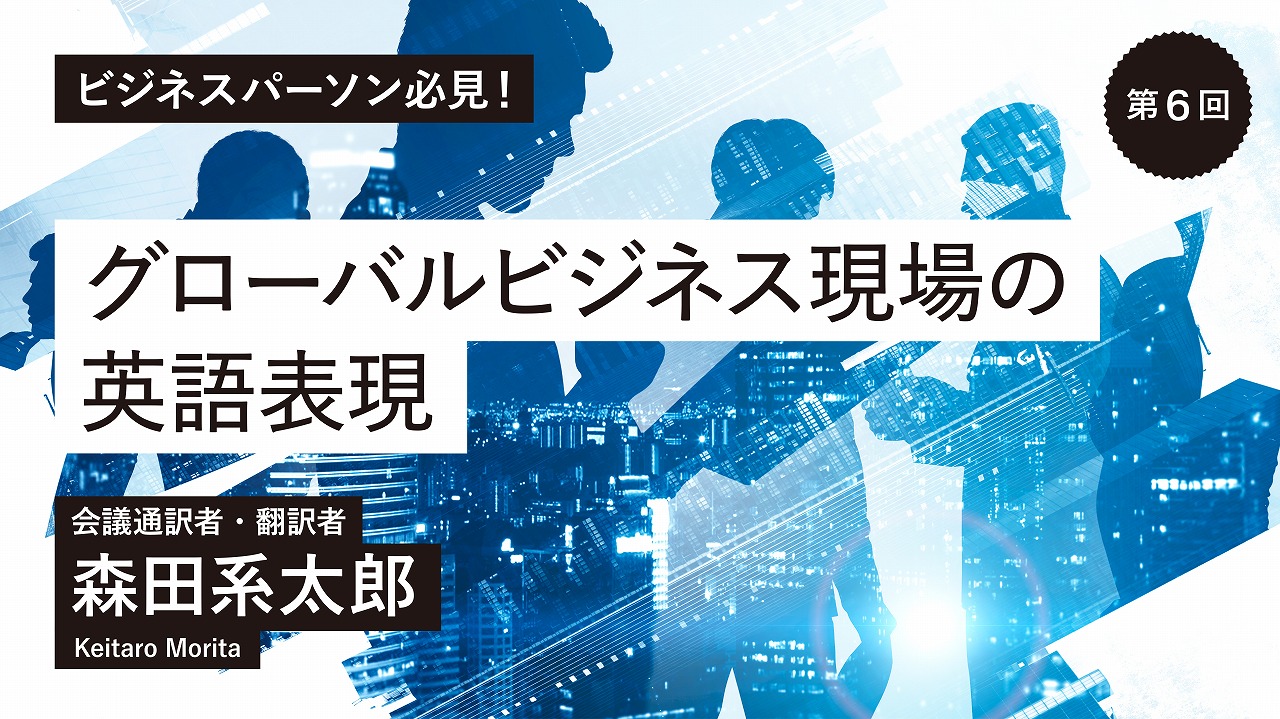季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
フランス語の出版翻訳を仕事とするようになって、20年以上になります。「千里の道も一歩から」ということで、なにが最初の一歩だったのかというと、まずは、初めて翻訳者としてお金をもらったときのことになるでしょうか。
実務からスタート出版翻訳へシフト
フランスに留学中、在仏日本人に向けの情報誌で翻訳事務所の求人をみつけ、応募したのがきっかけです。留学する前にも、翻訳講座に通い、多少の勉強はしていたのですが、いざ、仕事として取り組む翻訳は別物でした。まず納期が短い。そして責任が伴います。最初に訳したのは、アーティストのセルジュ・ルタンスに関するインタビュー記事でした。そのなかに、ルタンス自身の言葉として「仕事はやりながら覚えるもの」という一節があり、まさに今それを訳している自分の状況そのままではないかと思いました。
そして、2回目のデビューともいえるのが、その5年後、はじめて出版翻訳の仕事をしたときのことです。留学を終えて帰国したものの、実務翻訳で食べていくのは難しくなっていました。1990年代後半、日本企業の多くは欧州事務所をロンドンに集中させるようになり、フランス企業もユーロの導入以降、英語資料を用意するようになっていったからです。もともと関心はビジネスより文学にありました。そこで、実務翻訳で食べていけないならいっそ、文芸翻訳でやっていこうと腹をくくりました。
とはいっても、いきなり本が出せるわけではありません。まずは、東京日仏学院(現アンスティチュ・フランセ)の堀茂樹先生の文芸翻訳クラスに入りました。そこで、堀先生の翻訳デビュー作『悪童日記』(アゴタ・クリストフ、早川書房)は、先生自身が出版社に企画書を持ち込んで実現したものだと知ったのです。確かに、文芸翻訳の求人広告など滅多にありません。こちらから行くしかないのです。当たって砕けろとばかり、企画書を書き始めたものの、これはと思った本はすでに版権がとられていることも多く、なかなか結果に結びつきませんでした。
そんなとき、シビル・ラカンの『ある父親』という本と出会いました。精神科医の父をもつ私は、ジャック・ラカンの娘として父への愛憎を語る彼女に親近感を抱きました。最初のページを読んだときから、頭の中に訳文が浮かんだのです。レジュメを作成し、出版社に送ってから数カ月後、そろそろ諦めかけたころに一本の電話がかかってきました。こうして出たのが最初の訳書です。
好きな本でデビュー企画持ち込みは継続
振り返ると、この本でデビューできて本当によかったと思います。与えられた仕事ではなく、自分が好きな本でデビューすることができたのはとても幸せなことですし、自信がつきました。その後、お仕事の依頼がいただけるようになっても、自分から企画を持ち込むことは続けています。最新刊のロマン・ガリ『凧』(共和国)も、こうして実現しました。また、最初の本が「手記」というノンフィクションでありながら、とても私的な物語性のあるものだったことも幸いし、以降、さまざまなジャンルのお仕事がいただけるようになりました。
初めての訳書が本屋に並んだことはとてもうれしかったのですが、その直後、師匠の堀先生に「1冊で終わる人も多いからね。次の本が大事だよ」と言われたことは今でも覚えています。翻訳デビューという願いがかなったとき、そこで満足していてはプロではないと言われたような気がしました。実際、最初の1冊よりも、2冊目、そして、その後の継続のほうがずっと大変だったのです。
これを書いている今、世界はコロナ禍に揺れています。翻訳にできることは何でしょう。各国の最新情報を素早く翻訳することが求められています。カミュの『ペスト』が読まれていることからもわかるように、疫病と闘ってきた過去の記録を見つめ直すことも助けになります。千里の道の半ばにあって、これからが本当の勝負なのかもしれません。
※ 『通訳翻訳ジャーナル』2020年夏号より転載

フランス語翻訳者。仏文専修卒業後、翻訳者に。訳書は、マス『狂女たちの舞踏会』(早川書房)、シュペルヴィエル『海に住む少女』(光文社古典新訳文庫)、モレリ『戦争プロパガンダ10 の法則』(草思社文庫)、ガリ『凧』(共和国)など小説、ノンフィクションを中心に現在30冊ほど。
*『通訳翻訳ジャーナル』2020年夏号・掲載当時*