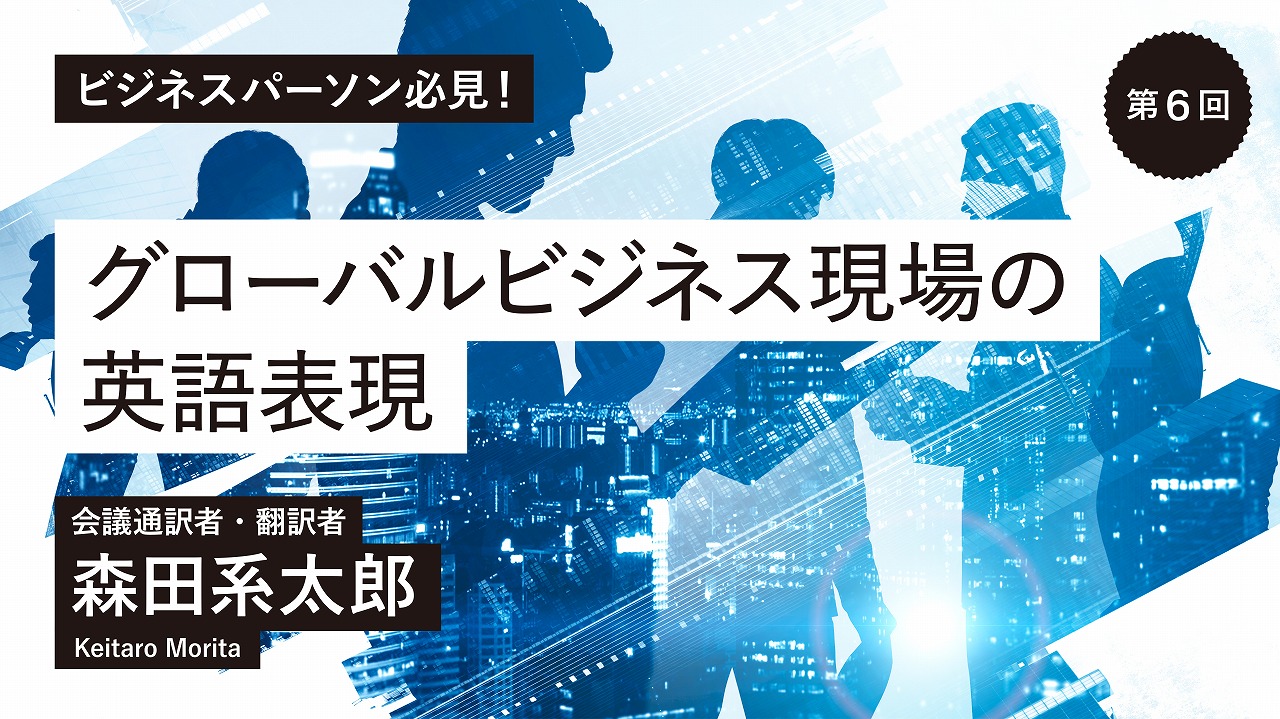季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
手に職をつけようと翻訳スクールへ
仕事上、一日のほとんどの時間パソコンに向かい、そのうえコロナ禍で外出もままならず、だいぶヤバそうだった胴回り(と、そのほかの部位)がますますヤバくなり、このままだと服をすべて買い替えねばならないという危機感のもと、部屋でできる痩せるダンスなるものをはじめました。ユーチューバーのたけまりちゃんこと、竹脇まりな氏の指導で(といっても彼女がいるのは画面の向こう)トレーニングをはじめたのです。これがめっぽう楽しくて、毎日最低20分は狭い部屋のなかでドタバタと運動しています。やっぱり楽しくなければ続かない、うん、うん、仕事もそう。翻訳だって楽しくなければ続かない。
というわけで、翻訳。読書が好き、英語を仕事で(当時)ちょっとだけ使っている、手に職をつけたい、などのぼんやりとした理由でいきなり翻訳学校に通いだしました。まわりの人間から見ると突拍子もない選択だったかもしれないけれど、本人は意気揚々とスクール主催のコンテストなんかにも挑戦していました。そのうちになんの翻訳をやりたいかを選ぶ時期になり、そこでよく考えもせず出版翻訳のコースを選んでしまったんです。
文芸翻訳の基礎を布施由紀子先生に叩きこまれたあと、田村義進先生に師事しました。田村先生のクラスはスクールのなかでも〝ゼミ〟と呼ばれるもので、優秀者は先生から下訳の機会を得て、その後は翻訳者として独り立ちする、というのが一般的なコースでした。
こう書くと簡単そうですが、現実はそうそううまくいかない。毎回〝どうひねりだしたらこんな訳に?〟みたいな珍訳のオンパレードで、あはは〜、と笑ってごまかすしかない日々が長くつづきました。あの修行の日々に、昔から好きで読んでいたミステリを、師匠の専門分野ということもあってさらに読みまくったのが、今につながっている気がします。
師匠からのご縁でYAミステリでフィクションデビュー
翻訳自体はちっとも上手にならなかったのに、やめようと思ったことはほとんどありませんでした。第一に、翻訳するのが楽しかったから。やっぱり楽しくなければ続かない。それとすばらしい仲間がまわりにいてくれたからです。みんなで酒を飲んだり、情報交換したり、愚痴を言いあったり。わいわいと街歩きをしたり、師匠の家に遊びにいって朝まで飲んだり、軽井沢でリゾートしたり。自分が翻訳の仕事をはじめられたのは、お世話になった先生方と翻訳仲間たちのおかげです。師匠には足を向けて寝られません(お住まいがどっちの方角かわかりませんが)。
その後、師匠から下訳の機会を、さらには師匠と交流のあるエージェントの方から仕事の打診をいただきました! 舞台はロンドン、夢破れたホームレスと野良猫の心温まる交流を描くノンフィクションで、邦題は『ボブという名のストリート・キャット』。それより以前にエージェントの方に〝猫と暮らしています〟と言ったのを先方が覚えていてくれて、それが仕事につながりました。いやあ、なんでも言っておくもんですね。出版にさきがけてテレビ番組でボブが取りあげられたこともあり、ありがたいことに訳書は版を重ねました。映画化もされ、プロモーションのためにボブが来日したのを昨日のことみたいに覚えています。残念ながらボブは2020年に亡くなりました。いまでもボブを思いだすとうるっときてしまいます。
現在はミステリを中心に翻訳しています。はじめて翻訳を担当したフィクションが『誰かが嘘をついている』(カレン・M・マクマナス/東京創元社)というYAミステリ。登場人物の高校生たちが愛おしくてしかたなく、物語にのめりこむように翻訳作業に没頭しました。その後に担当したYAミステリの『自由研究には向かない殺人』(ホリー・ジャクソン/東京創元社)は多くの読者のご支持をいただき、本屋大賞の翻訳小説部門で第2位に選ばれました。
なんにしても楽しいのがいちばん。これからも楽しみながら翻訳という仕事を続けていきたいと思っています。
※ 『通訳・翻訳ジャーナル』2023年冬号より転載

翻訳者。主な訳書『自由研究には向かない殺人』『優等生は探偵に向かない』(ホリー・ジャクソン/東京創元社)、『ミラクル・クリーク』(アンジー・キム/早川書房)、『ボブという名のストリート・キャット』(ジェームズ・ボーエン/辰巳出版)など。