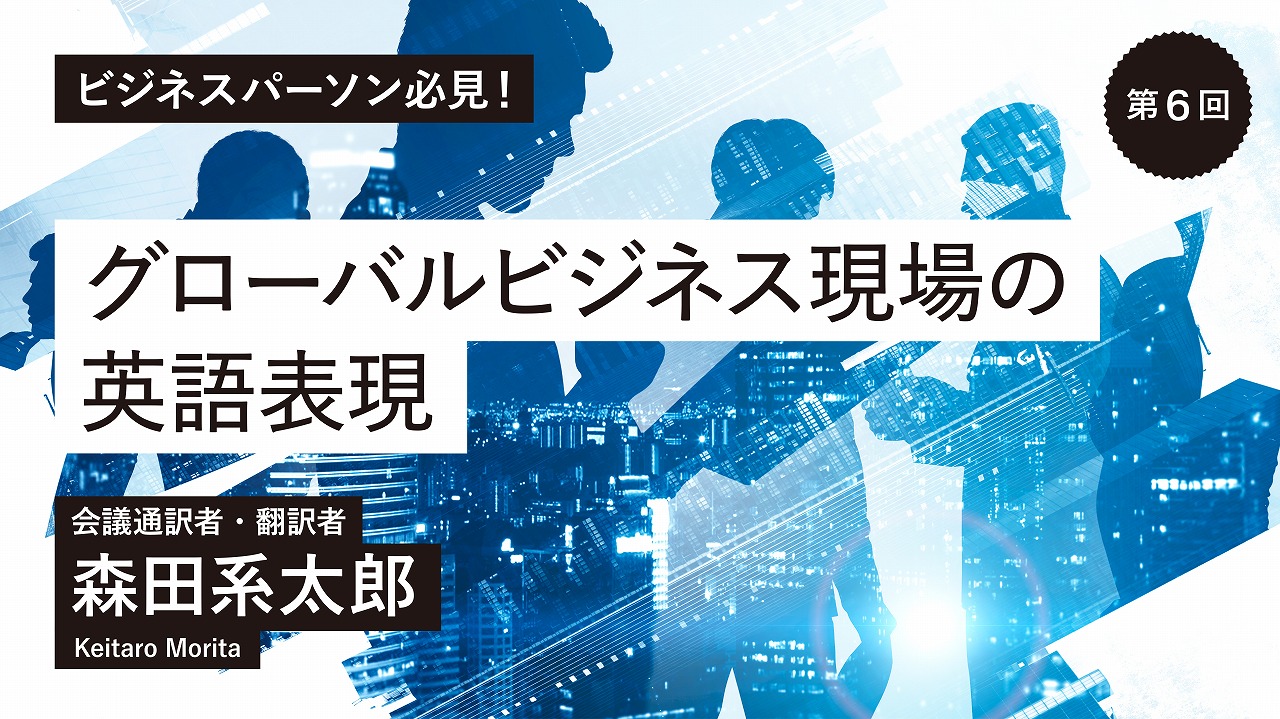季刊誌『通訳翻訳ジャーナル』の連載、翻訳者リレーコラムをWebでも公開しています!
さまざまな分野の翻訳者がデビューの経緯や翻訳の魅力をつづります。
幼少期の読書体験で気づいた言葉の魔術性
Twitterをのぞくと、朝ドラや大河ドラマが共通の話題になっている。ひとつのフィクションをめぐって盛りあがることができるのは、私たちがみんな違って、けれど同じであることに由来し、その根底に身体性がある―とこの数年ヨガにはまっている私は思う。
同業者〝あるある〟で、小さい頃から本を読むのが好きだった。本に恵まれ、自宅には赤箱入りの小学館『世界の文学』があった。児童文学はもちろん、『オデュッセウス物語』や『天路歴程』、『阿Q正伝』等も収録され、〝文学〟を謳うだけのラインアップだった。『秘密の花園』と神話が特に好きだった。最終巻が日本編で、その一編『潮騒』には焚き火をはさんだ若い男女の挿絵が入っていた(と思う)。もう一編が『しろばんば』、この渋い小説によって小学生高学年の私はヘレン・ケラーが手に水を浴びながら〝水〟の実体と言葉を結び合わせたのと似たような体験をした。本筋とは無関係に出てきた〝結核〟という言葉から、それが人から忌避される伝染性の病であり、自分が小学1年生で1年間入院する原因であったことを初めて自分のこととして理解したのだ。
この入院の影響は大きかったとみえ、中学に入ると、大江健三郎さんの短編『鳩』で〝ユーリカ〟体験が訪れた。この短編の舞台となる少年院には、私が入院していた山中の療養所と同じ質感があった。貧しさ、密やかな子どもだけの世界、子どもだけの遊び、世間から隔絶された閉塞感、鬱屈、澱んだ空気、苛烈ないじめ。堆積して手つかずだった幼少時の体験が、それを知るはずのない他人の手で表現されていた。思春期の私はその事実に驚くと同時に、幼いながら言葉の持つ魔術性に陶然となった。
キングを訳したいと翻訳の勉強を開始
以来、悲しいにつけ苦しいにつけ、出会うべき本を探すことが習い性になった。大学卒業後いくつか職についたのち、本を扱う仕事がしたくて、デザインの勉強と翻訳の勉強で迷った。決め手は原書で読んだスティーヴン・キングの『IT』だ。異国の地に暮らす少年少女の逃げ場のなさや絶望が距離や言語の違いを越えて響き、翻訳という仕事に魅力を感じ、いつかキングを訳したいと思った。
それで〝寺子屋〟を標榜する小規模な翻訳学校に通うことになる。一線で活躍される複数の先生に教わり、最後がキングの訳書も多い矢野浩三郎先生だった。本業をこなしつつ、おもに週末を使って下訳やリーディングの仕事を積み重ねる日々が長く続いた。元来、飽き性なのだけれど、翻訳は続けられた。最初に教えてくださった山本光伸先生に言われた、「きみは賢いから、途中でうまいことを言って翻訳をやめるかもしれない」という言葉が、くさびになった。
デビューは2000年1月、姉弟子の加藤洋子さんが引っ張りあげてくださった。「幸運の女神には前髪しかない」という言葉は、洋子さんに教わった。初訳書の見本が自宅に届いたときは、うれしくてうれしく
て家のなかをぐるぐる歩きまわった。
それから20数年になるが、いまだにキングは訳せていない。訳したかったのはホラーや幻想怪奇小説だったけれど、実際はロマンスの訳書が多い。だが大違いに見えるホラーとロマンスは、意外に似ている。どちらもエモーショナルで、心と体に訴える部分が肝心なことだ。そして数年前、本の神様のはからいか、『沼の王の娘』という作品がめぐってきた。アンデルセンの童話が随所に引用され、読む人を選ぶ神話的な作品だった。この本を理解するにあたっては、同居の家族を失ったあと、聖書やユングに没頭したことが生きたように思う。
ユングは個性化を促すものとしてヨガにはまったとされる。私がヨガを始めたのは身体のためだったが、いま教えるようになってみると、ヨガを伝えることと翻訳は重なる。どちらも媒介するのは私だが、私には肉体や呼吸や記憶や理性など、複数の層がある。私でいて私でない域、より深い層にタップできたとき、普段の私からは出てこない表現が汲みだされる。締切に追われる仕事ではあるけれど、そのことを心にとどめて、原文に虚心に向きあいたい。
※ 『通訳・翻訳ジャーナル』2022年夏号より転載

国際基督教大学教養学部・社会科学科卒。英米文学翻訳家。主な訳書に『沼の王の娘』(ハーパーコリンズ)、『欺きの仮面』(集英社)、『明日のあなたも愛してる』(二見書房)、『世界の神話大図鑑』(三省堂)他多数。近所の映画館に通い、下手な庭仕事にいそしみ、買ったばかりのオーブンでお菓子を焼くのが最近の楽しみ。パソコンを持って放浪の旅に出たいものです。