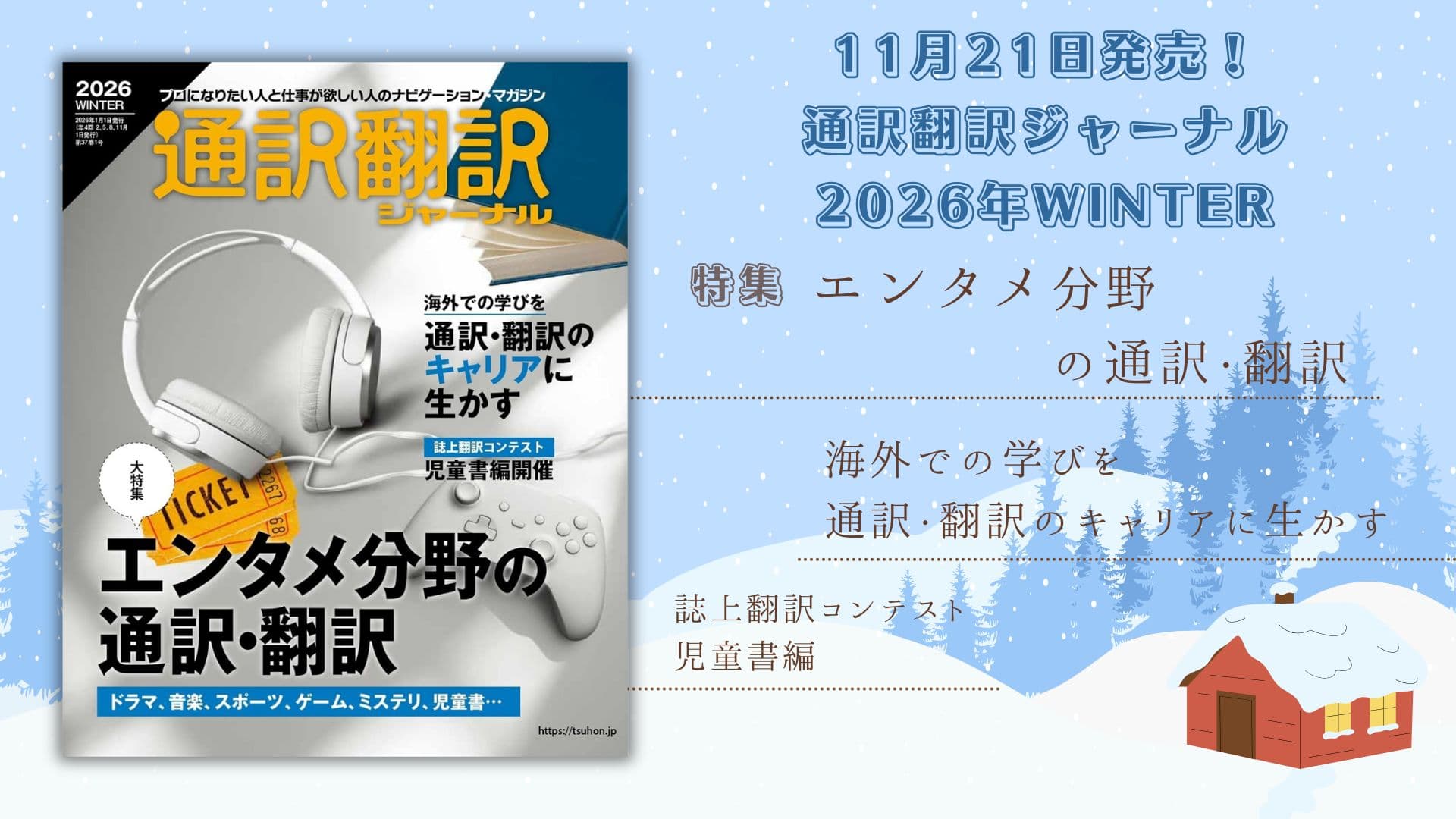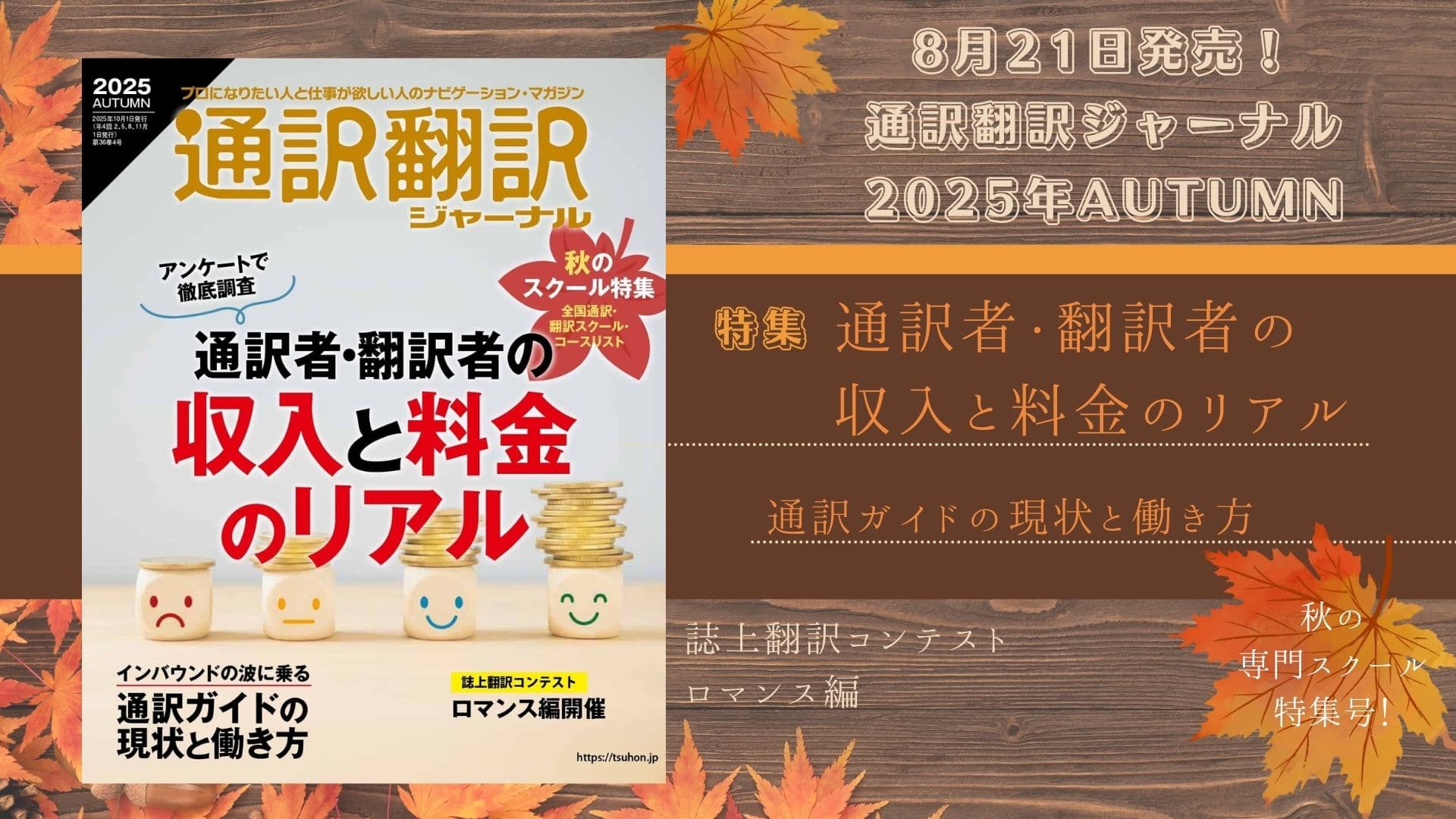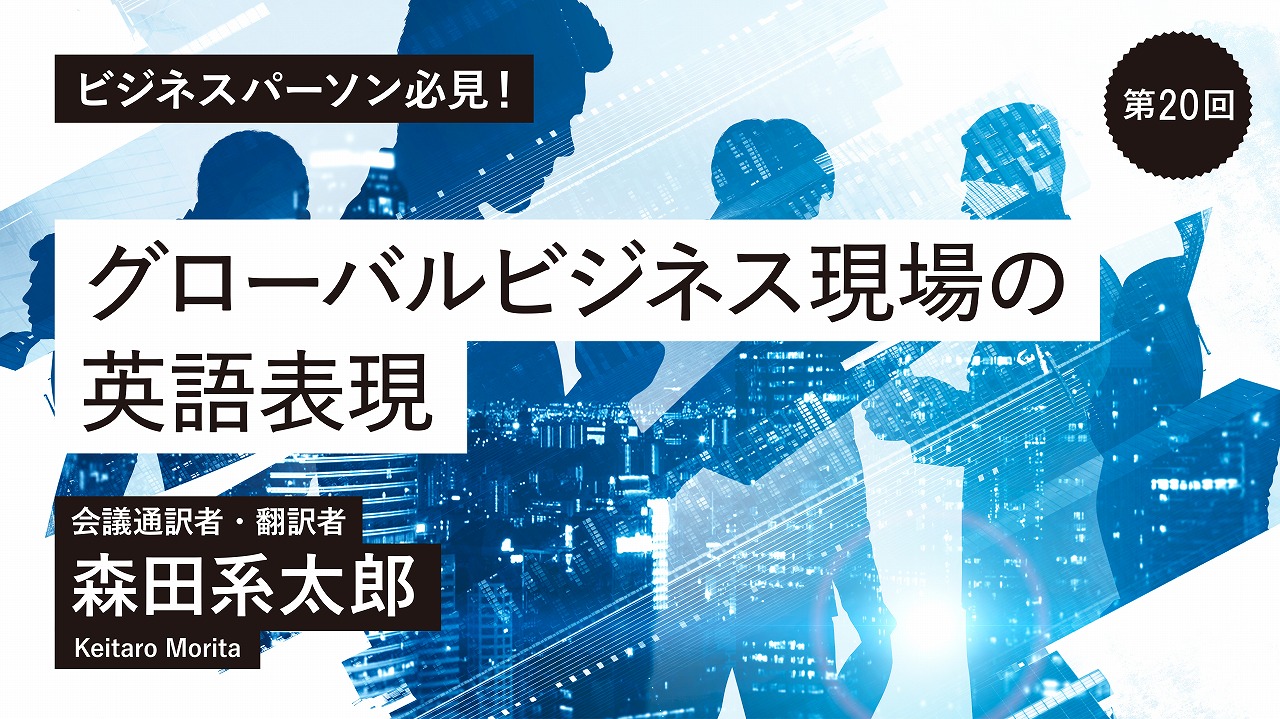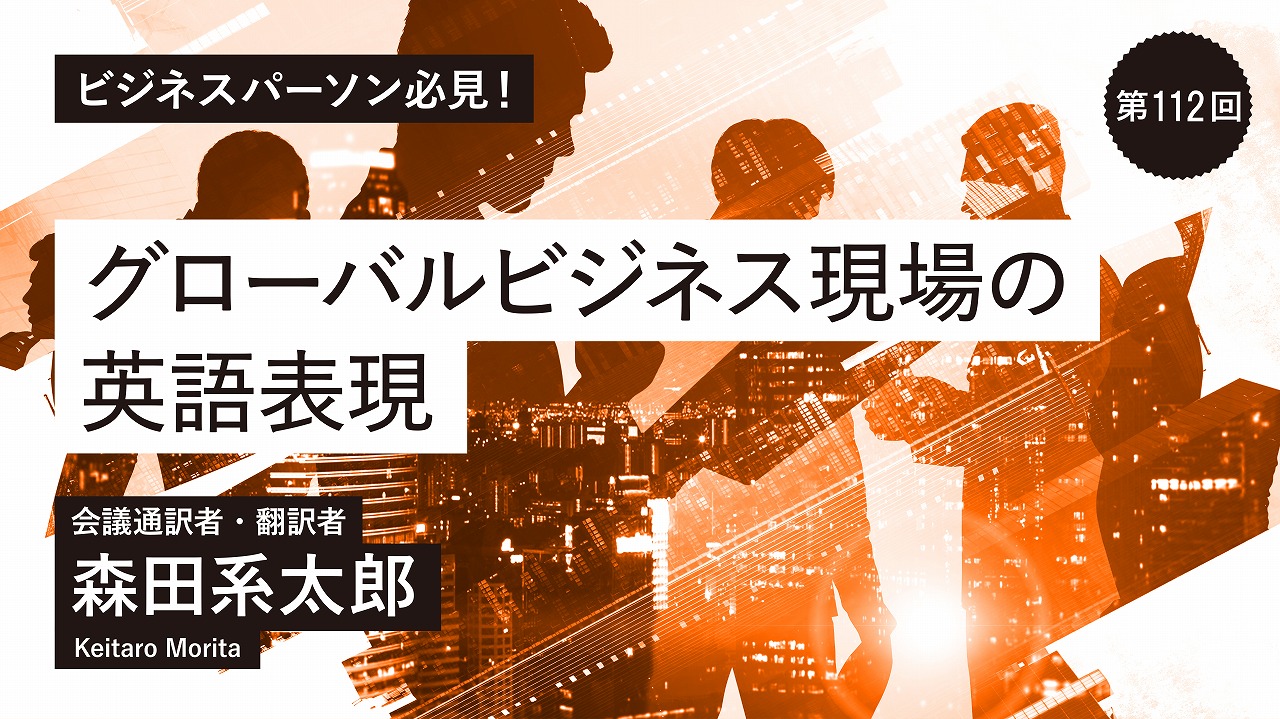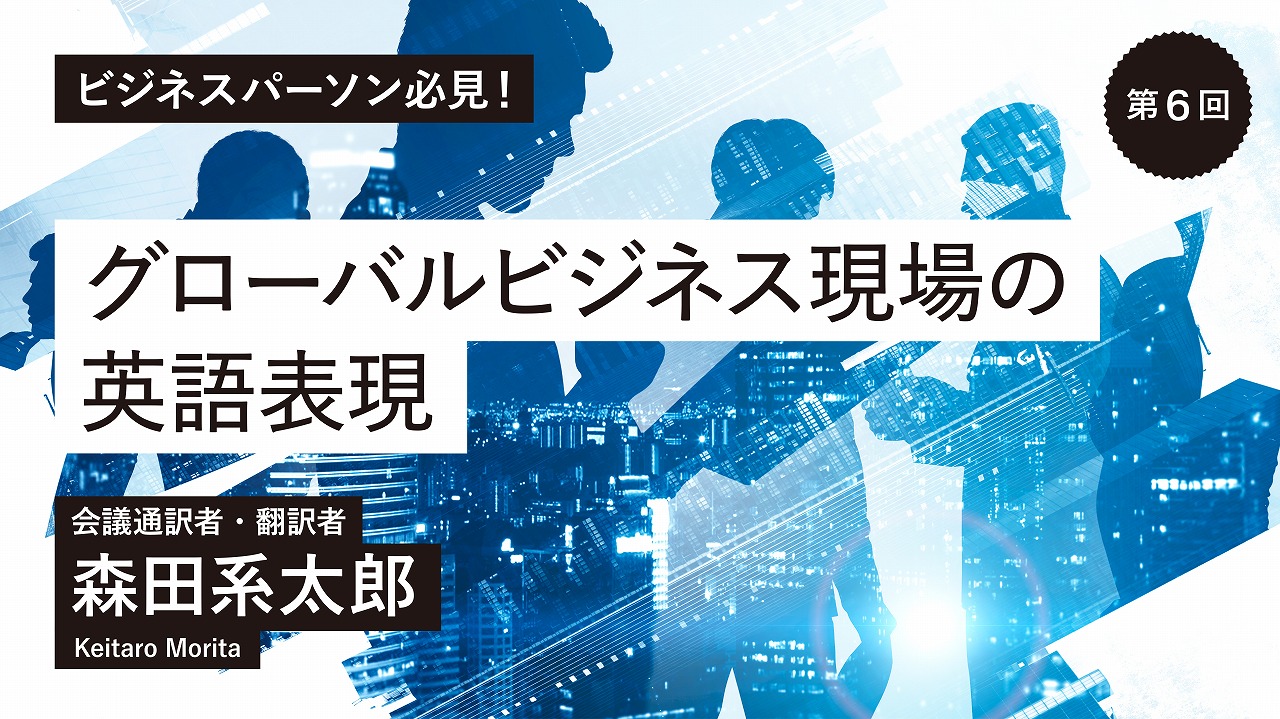通訳業界に関わって30年以上で、現在は一般社団法人 通訳品質評議会 理事 を務める藤井ゆき子さんが通訳者のキャリア形成について解説します。
外国人労働者の増加により需要が増すコミュニティ通訳
前回のコラムで「コミュニティ通訳」について少しご紹介いたしましたが、今回は海外での取り組みについてご説明したいと思います。なおここでは広義の意味での「コミュニティ通訳」で、いわゆるsocial/public services interpretingも含んで説明をしています。
「コミュニティ通訳」をとりまく海外の動き
近年、翻訳や通訳について国際標準化機構ISOが国際規格作成にむけて活動をしているのはあまり知られていませんが、通訳については2014年12月に「コミュニティ通訳のガイドライン」(ISO13611)が発行しており、2023年の現在では発行5年後の見直し作業が行われています。
このガイドラインでは、コミュニティ通訳を明確にプロフェッショナルでなくてはならないと定め、場面設定においては、学校を含む行政機関、医療機関、保険や不動産関連、各種イベントや祭典、災害緊急時などが含まれています。
また必要な能力の規定も細かく規定されていますが、なかでも手続書類などの説明を想定しているのか sight-translationの能力や、問題解決に尽力すること、コミュニケーションを円滑に進める能力など、特徴的な記述がありました。
詳細についてはISOのホームページのカタログのページから、発行済みの規格は購入ができますので、ご興味のある方はアクセスしてみてください。
現在ではコミュニティ通訳から派生して、より専門性のある司法通訳や、医療通訳についても議論が進み、それぞれISO20228が2019年4月に、ISO21998が2020年12月にまた会議通訳についても議論がされ2022年1月に発行されています。
特に司法通訳については、世界人権宣言を元に欧米を中心に、国籍を問わず公平な裁判を受ける権利についての法律や宣言などの公式文書が存在しており、その中で司法通訳・翻訳についての規定が定められている状況です。
医療についてもWHOを中心に患者の権利についての規定があり、各国の患者の権利に関する規定等を基に医療通訳の制度や認証をしている国や自治体があります。
多言語社会であるEUを始め、移民が多いオーストラリア、カナダ、アメリカなどは現場の必要性から議論が開始されたと認識していますが、それ以外でも南米ではアルゼンチンやコロンビアなどの取り組みも進んでいるようです。
2018年からISO関連の国際会議に参加していますが、上記の各国の取り組みを具体的に伺うことができ、アジアでは日本、韓国、中国、タイが参加していますが、とりわけ中国が国際規格に積極的に取り組み、通訳や翻訳教育に力をいれていることも認識できました。
コミュニティ通訳の存在が認知されていなかった日本
一方、日本の現状はというと、そもそも通訳全般について認証制度はなく、国家試験や資格制度もなく、欧米中韓のように大学で通訳・翻訳と明示された学位をとれるところがほとんどありませんでした。会議通訳の訓練はエージェントの付属通訳学校が中心で言語も日英が中心です。さらにいえばコミュニティ通訳の存在自体が一般的に認知されていないという状況でした。
昨今、政府は新たな在留資格を設け、外国人労働者の流入拡大を認める方針を示し、将来的に50万人超の受け入れ増を見込んでいます。また訪日外国人旅行者についても積極的に観光立国政策が取られようとしています。
その政府の動きもあるためか、近年では大学病院を併設しているような大学で医療通訳の講座や大学院で学位を取れるコースが開設されたり、一部の公立大学ではコミュニティ通訳の研究をする大学院の講座が開講されるようになりました。
企業内や企業間のビジネス通訳や国際会議・セミナーの会議通訳はグローバル経済を牽引し、日本が国際社会の一員としてメッセージを発信していく大切な役割を担っていることは言うまでもありませんが、個人として訪日している、また在留している外国人の方々が日本でどういう体験をするかは、日本全体のイメージを左右することになり、結果的にはビジネスにおいても大きな影響が出てくると思います。
彼らの生活をサポートするコミュニティ通訳は、公平で安心に日本で過ごせるためのインフラとしても育成や確保に真剣に取り組んでいくべき課題だと思っています。
通訳をめざしている皆様や、すでに通訳者として活躍している皆様がキャリアの一つとして今後選択できるように、私も微力ながら所属している一般社団法人通訳品質評議会で活動を進めて行きたいと思います。
★「通訳者のキャリア形成」の記事一覧はこちら

慶應義塾大学卒業後、日本外国語専門学校(旧通訳ガイド養成所)に入職。広報室長を経て、1987 年(株)サイマル・インターナショナルに入社、通訳コーディネーターとして勤務後事業部長を経て2012年11 月に代表取締役就任。2017 年4 月末に退任後、業界30 年の経験を生かしフリーランスでコミニュケーションサービスのアドバイザーとして活動。2017 年10 月より一般社団法人通訳品質評議会(https://www.interpreter-qc.org)理事に就任。