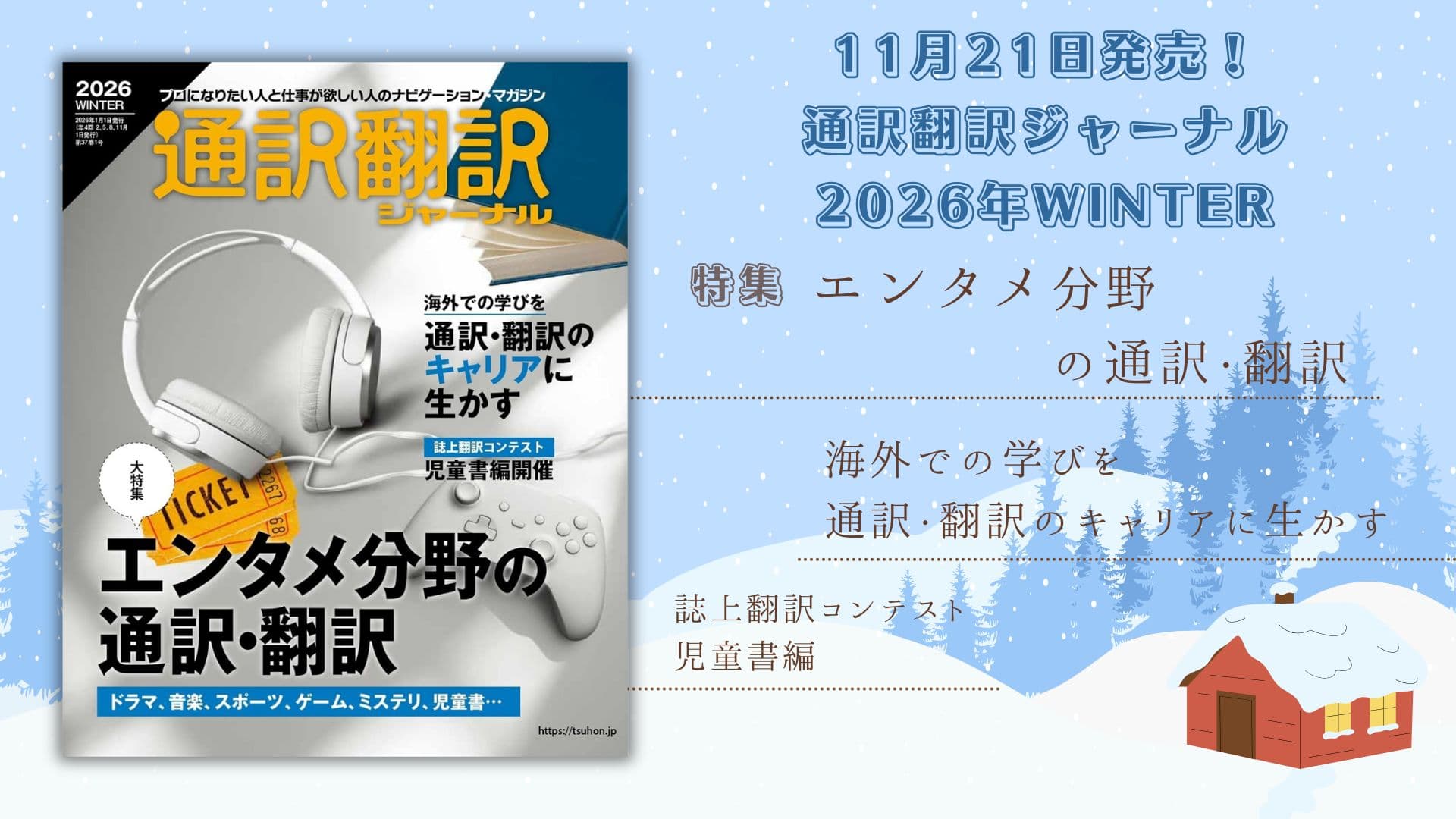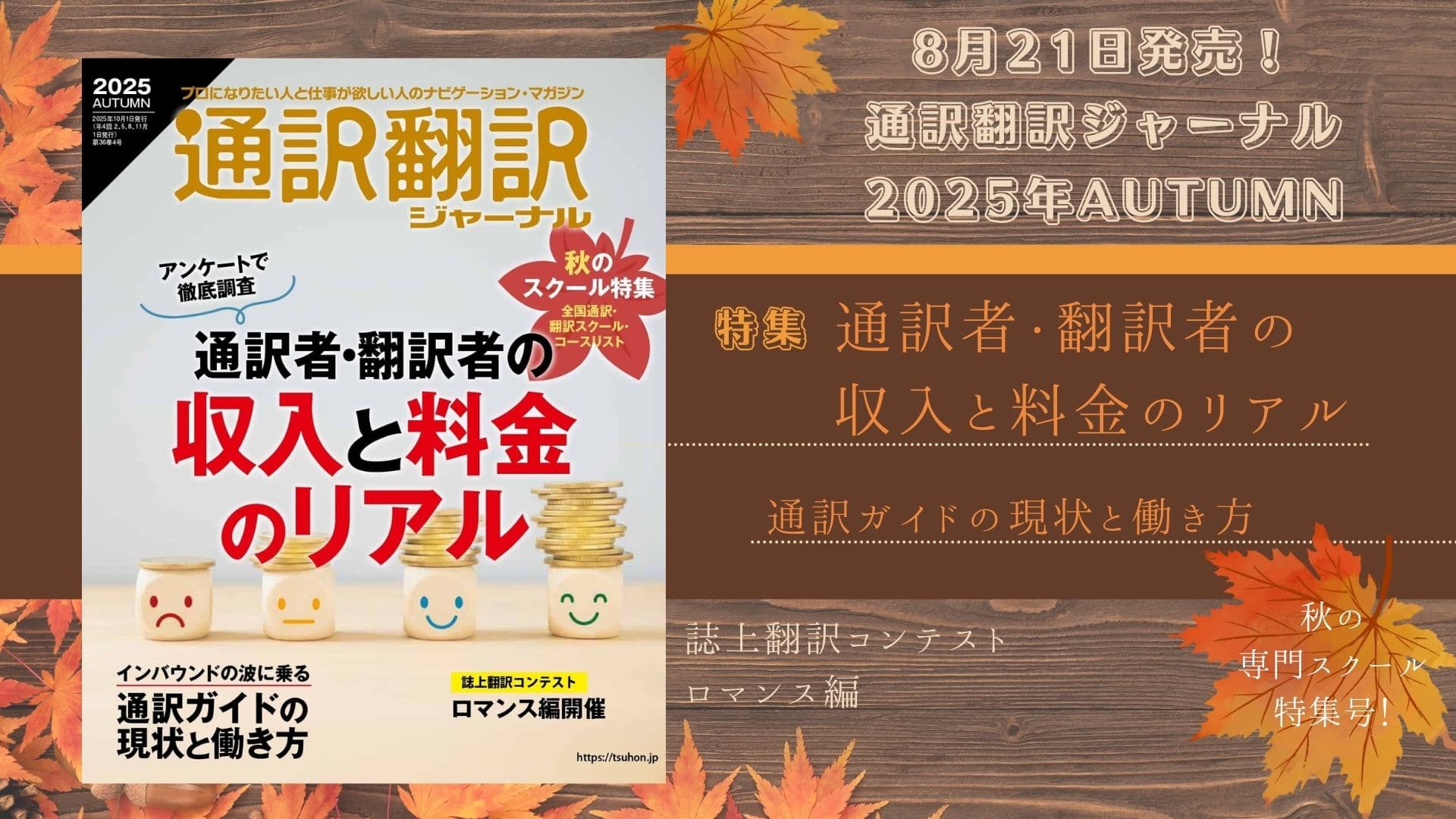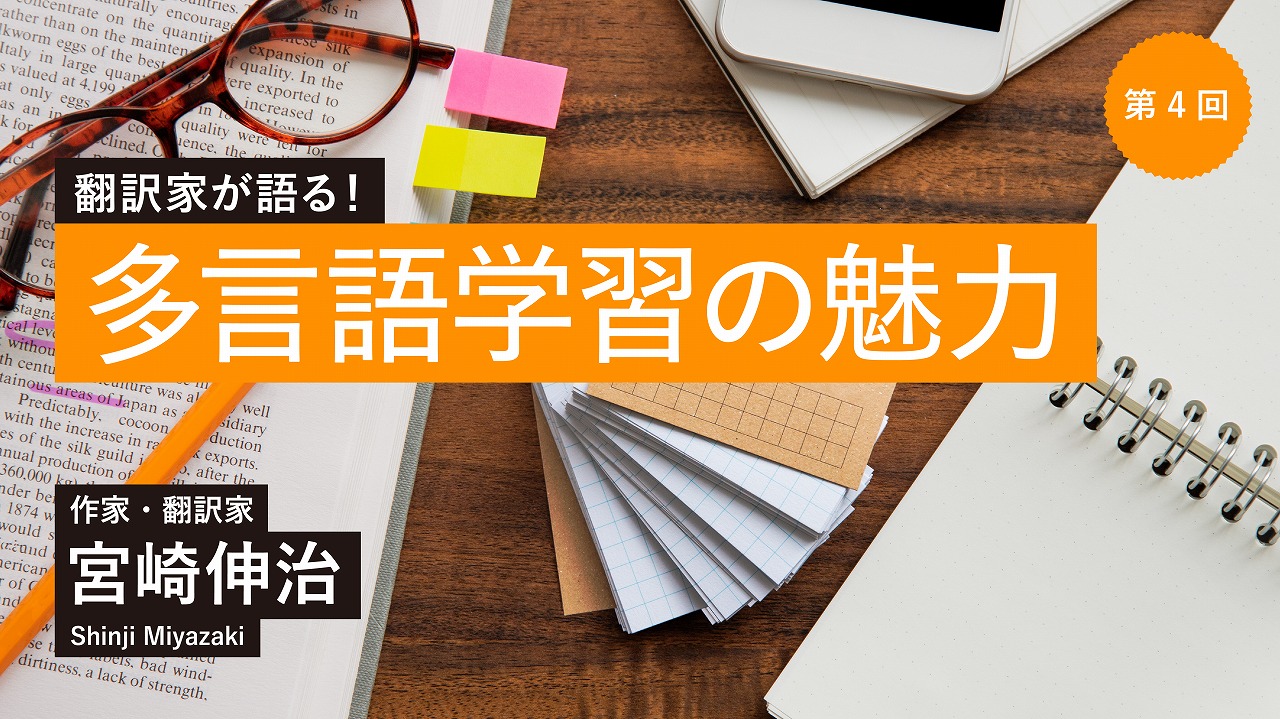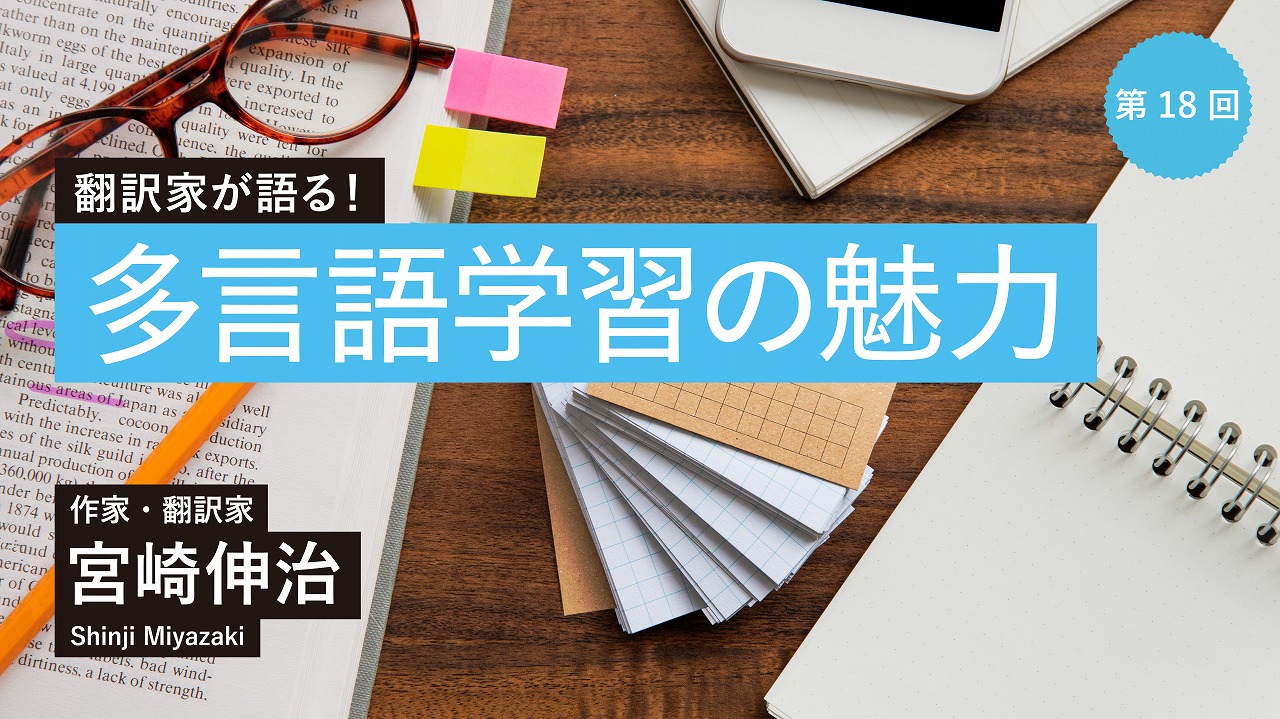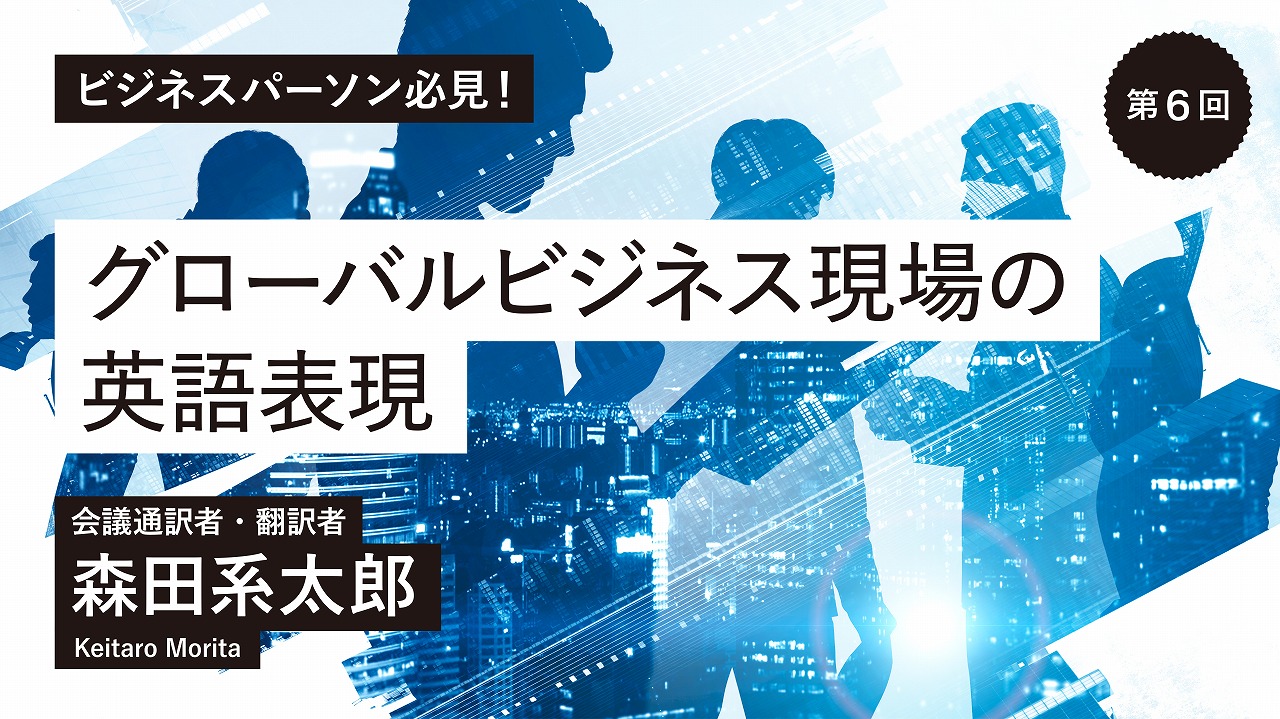通訳業界に関わって30年以上で、現在は一般社団法人 通訳品質評議会 理事 を務める藤井ゆき子さんが通訳者のキャリア形成について解説します。
コミュニティ通訳は、外国人のくらしをサポートする仕事
みなさんはコミュニティ通訳と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
大まかに説明するとすれば、その国の自国語ができない市民に対して、暮らしの中での言語サービスを行う役割になります。
具体的には、在留外国人や訪日外国人が行政窓口や病院、警察、学校などで必要な手続きやサービスが受けられるための言語サポートがコミュニティ通訳です。
コロナ前2019年の統計では、在留外国人の人数は293万人、訪日外国人は3000万人を突破しました。コロナ禍で一時的に落ち込みましたが、今後は、生産労働人口が減少していく日本にとっては労働力としても、観光立国政策強化の方向性からも、この増加傾向は変わらないと思います。仕事や会議以外の場所でも、外国人の方々と遭遇することがもはや日常となっていると思います。
残念ながら、ビジネスや会議通訳とは異なり、日本においてその存在はあまり認知されておらず、その多くはボランティアや家族・知人に頼っている現状です。
それは何故かと言えば、通訳サービスの対価を保障する仕組みが現在ではあまり整っていないことが大きな原因だと思います。ビジネスや会議については概ね通訳料の相場があり、クライアント側が負担する事になりますが、コミュニティ通訳の場合は司法の現場を除いてはいったいどこが負担してくれるのかという問題があります。
現状では非営利団体が登録者を安価で手配することも多く、外国人側に負担を求める形なので結果としてボランティアや家族・知人に落ち着いてしまうことになります。おそらく、なんとなく外国語ができればなんとかなるのではないか、という利用者側の意識も大きいのかもしれませんが、ビジネスや会議通訳と比べて簡単かというとそうとも言い切れないところが多いです。
ビジネスや会議の場合は参加者が目的を事前に理解していることや、お互いに使うビジネスの語彙についてはある程度共通の概念が持てるものが多いというがあります。また、概ね参加者の知的レベルの差が大きくないことが多いです。
国籍や文化の違いが、コミュニティ通訳の難しいところ
一方、コミュニティ通訳についての現場を想定してみてください。
たとえば病院の場合、当たり前ですがどんなバックグラウンドを持ったどんな症状の患者さんが来るかは、事前にはわからないことが多いです。そして病院側のスタッフと患者さんには、治療行為についての双方が持っている情報と知識の差が大きいということがあります。
また、同じ英語を話せる外国人であっても、国籍だけでなく育った地域の文化背景によっては同じ単語を使っても、言い回しや語彙の意味が異なる場合もあります。
もちろん中国語やスペイン語等も同様のことがあります。
さらに難しいのは病名ひとつとっても、患者さん側の文化において対応する訳や概念がないという場合もあり得ます。たとえば、あるアフリカ出身の方の育った文化において「うつ病」という概念がそもそもなかった事例を読んだことがあります。また精神疾患についてはタブー視される社会背景もあります。
これだけでも、間にたって通訳するのは結構難しい、と思われるのではないでしょうか。
これはあらゆる行政窓口でも同様のことが想定されます。とりわけ、医療や司法については、観光立国や多文化共生社会をめざす上でも、日本語を解さないというだけで基本的人権が守られないという訳にはいきません、いわば現代社会の重要なインフラとして認識されるべきだと考えます。
実際、移民が多い海外では医療や司法通訳については、資格制度や認証制度がある国や自治体があります。また日本においても少しずつ取り組みを始めている兆しがあることは事実です。
近い将来、コミュニティ通訳という分野がキャリア選択の一つになるような社会にしていかなくてはならないと思っています。
次回はこの取り組みについて少しご紹介できればと思います。

慶應義塾大学卒業後、日本外国語専門学校(旧通訳ガイド養成所)に入職。広報室長を経て、1987 年(株)サイマル・インターナショナルに入社、通訳コーディネーターとして勤務後事業部長を経て2012年11 月に代表取締役就任。2017 年4 月末に退任後、業界30 年の経験を生かしフリーランスでコミニュケーションサービスのアドバイザーとして活動。2017 年10 月より一般社団法人通訳品質評議会(https://www.interpreter-qc.org)理事に就任。