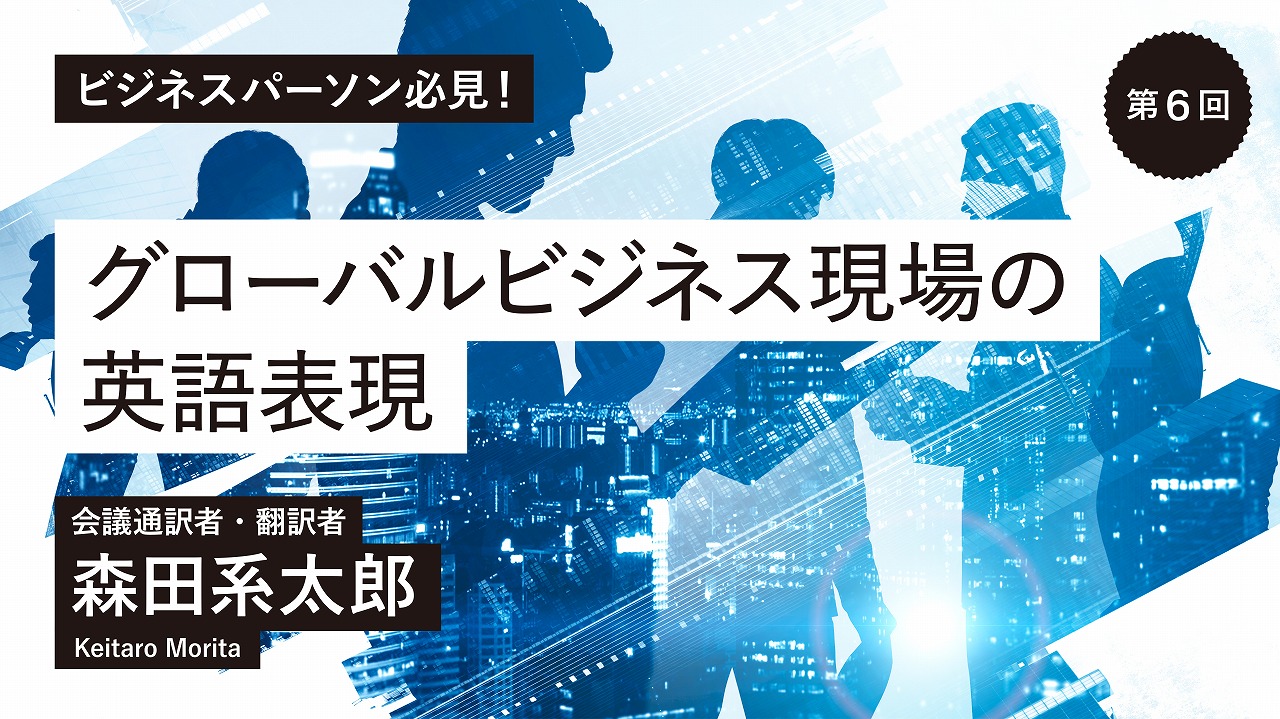通訳者が登場する歴史小説に
ロールモデルを見いだす
仕事は大なり小なり、読書に影響を及ぼす。
放送通訳者としてまだ駆け出しだった頃、智幸さんは『冬の鷹』(吉村昭)と『二つの祖国』(山崎豊子)という2つの歴史小説を読み、作中に登場する通詞や通訳たちの生き様やあり様に「通訳としてのロールモデルを見いだそうとしていた」という。

「『冬の鷹』は『解体新書』の実質的な翻訳者である前野良沢の物語で、オランダ語通詞が登場します。一方の『二つの祖国』は、東京裁判で通訳チェックを務めた日系二世の伊丹明をモデルにした小説です。自分が通訳者になり、通訳者の視点で本を読んだのは、この2冊が最初だったと思います」
早苗さんは社会人になって以降、小説をほとんど読まなくなった。仕事がら時事関連の本を読むことが多く、ニュースに応じて読む本のテーマを変えていく。では、“根無し草”なのかといえば、そういうわけでもない。
「聖書、シェイクスピア、ギリシャ神話。この3つは英語に関わる仕事をする以上、ライフプロジェクトとして読んでいかなければと思っています」

重要な箇所に線を引き、読書ノートをつけるという「熟読派」の智幸さんに対し、目次やあとがきを手がかりに自分が必要とする箇所を選び、それ以外は斜め読みするという「メリハリ派」の早苗さん。本の読み方まで大きく異なるが、そんなお二人にとって読書とは?
「知見を広め、考えを深め、できればその考えを行動で具体化していく。そんな人間らしい生き方をするために必要なものだと思います」(智幸さん)
「水や空気と一緒で、なくては生きていけないものですね」(早苗さん)

※ 『通訳翻訳ジャーナル』2019年春号より転載 取材/金田修宏 撮影/合田昌史