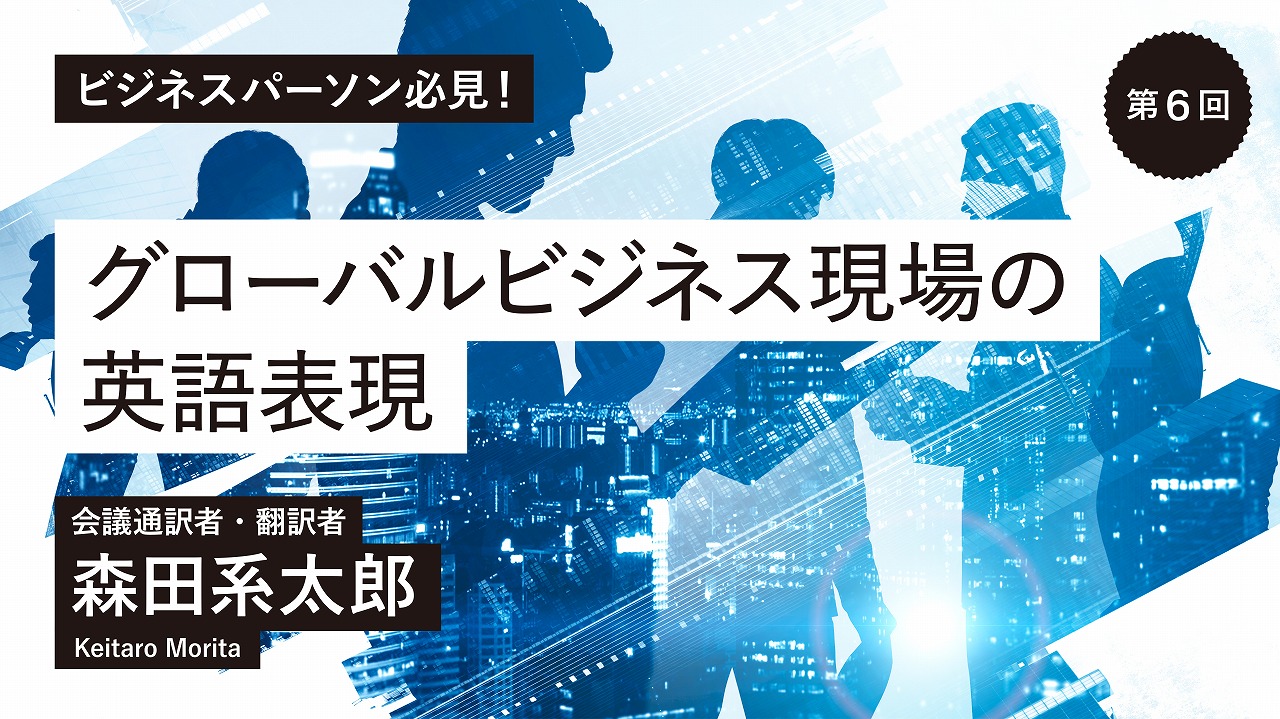Contents
日本での通訳・翻訳需要は英語が大部分を占めており、中国語、フランス語など、学習者の多い言語がそれに続いていますが、それ以外の言語を専門とする通訳者・翻訳者も多数活躍しています。そういった学習者の比較的少ない、マイナーと呼ばれがちな言語=「その他の言語」を専門とする通訳者・翻訳者のお仕事を紹介します!
持ち込み作品で日本翻訳大賞を受賞
現代ポルトガル文学の魅力を日本に伝える

ポルトガル語翻訳家。上智大学ポルトガル語学科卒業。訳書にパウロ・コエーリョ『ブリーダ』『ザ・スパイ』『不倫』(KADOKAWA)、ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ『忘却についての一般論』『過去を売る男』(白水社)、ジョゼ・サラマーゴ『象の旅』(書肆侃侃房)、ゴンサロ・M・タヴァレス『エルサレム』(河出書房新社)など。ジョゼ・ルイス・ペイショット『ガルヴェイアスの犬』(新潮社)で第5回日本翻訳大賞を受賞。
中学生での出会いを経て
大学で本格的にポルトガル語の勉強を開始
2018年に出版された『ガルヴェイアスの犬』で第5回日本翻訳大賞を受賞し、2021年には絵本も合わせて3冊の翻訳書を世に送り出した木下眞穂さん。ポルトガル現代文学の翻訳者として今や代表的な存在だが、中学生のときに初めて訪れたポルトガルに、実は最初はあまり良い印象がなかったのだという。
「父の仕事の都合で、中学2年生のときに1年間、家族でリスボンに住むことになりました。そのくらいの年頃だと、おしゃれでキラキラしたものが好きですよね。でもポルトガルは当時、すこし田舎っぽくて全然そんな雰囲気が無くて、『なんてとこに来ちゃったんだ…』とがっかりしました(笑)」
リスボンで通っていた学校の授業は英語だったため、ポルトガル語は勉強しないまま日本に帰国。しかし、だんだんと「せっかく外国にいたのに、もったいなかった。ポルトガルについてもっと知っておけばよかった」という気持ちが大きくなり、高校卒業後はポルトガル語を学ぶため、上智大学ポルトガル語学科に進学した。
「父から『ポルトガル語をやれば留学しても良い』と言われたことも、きっかけの一つです。やるからには、ちゃんと話せて書けるようになるという目標は持っていました。小さい頃から海外文学が好きだったので、翻訳者という道もこの頃から意識はしていました」

大学2年次には中部の港町アヴェイロ、4年次にはリスボンに、それぞれ1年間留学した。帰国後は、留学中に知り合った人の紹介で、ポルトガル政府観光局で2カ月ほどアルバイトをすることに。その仕事が終わると、次はポルトガル大使館のアルバイトを紹介され、卒業後もそのまま働き続けて、途中からは正規職員になった。当時は1993年に日本とポルトガルが友好450周年を迎える関係で、記念イベントがいくつも企画されており、その準備や運営などに多く携わった。
「大使館では、日常的に業務で通訳・翻訳をしていました。翻訳で多かった文書は文化イベントなどの資料や解説文、内部書類やレターなど。夫のシンガポールへの転勤と妊娠を機に退職するまで約6年間務めたのですが、最後の年にはポルトガル映画祭を初開催することになり、字幕の監修も任されました」
映画祭をきっかけにブラジルやポルトガルの字幕監修もときどき頼まれるようになったが、退職後の約10年間はあくまで子育てに専念し、仕事はたまに依頼が来た時だけ、というペースでこなしていた
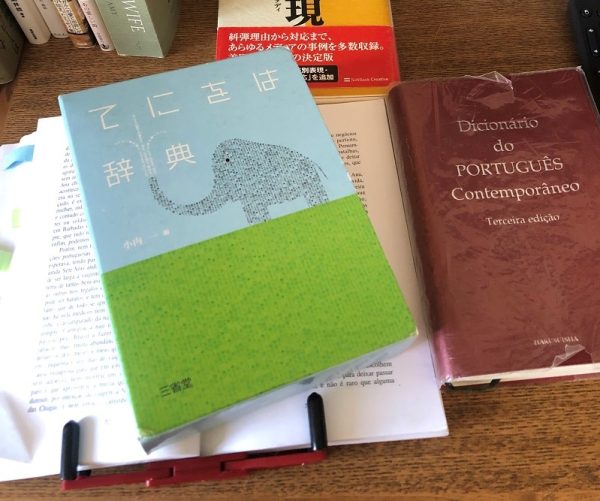
サラマーゴがきっかけで
ポルトガルの純文学にめざめる
仕事でばりばり翻訳をこなしていた木下さんがポルトガルの文学に興味を持ったのは、大使館を退職後、シンガポール在住中に、ジョゼ・サラマーゴの『白の闇』を原書で読み通したことがきっかけだったという。
「10代の頃に海外ミステリにはまってから、ずっとエンタメ系の作品が好きだったので、大学時代にポルトガルの純文学作品を読んでも、おもしろいと思えなかったんです。初めてポルトガル語で全編を読んだ小説が『白の闇』でした。サラマーゴの文体は複雑で難しいのですが、それでもぐいぐい引き込まれるスリリングな物語に衝撃を受けました。これがきっかけでポルトガルの文学作品に興味が出て、ネットでおもしろそうな原書を探して、取り寄せて読むようになりました」
木下さんがシンガポールから帰国後、1998年にサラマーゴがノーベル文学賞を受賞した。木下さんにとっては嬉しいニュースだが、当時はまだ邦訳が1冊も出ておらず、日本でサラマーゴを知っている人はほとんどいない。どうしても誰かとこの感動を分かち合いたくて、大使館時代に仕事でやり取りをしたことがある、ポルトガル語・文学研究者の岡村多希子氏に手紙を送った。すると、NHKでサラマーゴの特集番組を作るため、資料の翻訳を手伝ってくれないかと声をかけられ、サラマーゴの膨大な日記を読み、番組で使えそうな箇所の選定と、その下訳を担当することになった。
この仕事を経て、やはり翻訳はおもしろい、機会があれば出版翻訳もやってみたいという気持ちがだんだんと膨らんでいった。子育てのかたわら、大学の友人や、大使館時代の知人に、翻訳の仕事をしていることを折に触れてアピールするようにした。
「特にマイナー言語の人は、周りに『翻訳をしている』と伝えることがとても大事です。思わぬ縁が、仕事につながることもありますので。最初の訳書となった『永遠の絆』は、知人から翻訳者を探していると声をかけられて、訳を担当することになりました」

2009年に出版された『永遠の絆』はブラジルの作家による小説で、当時流行していたスピリチュアル系のラブストーリー。出版翻訳は初めてだったが、「大まかな文体はこちらで直す」と急かされ、作品とじっくり向き合う時間がない中で何とか翻訳を終えた。
すると、その後すぐに別の知人から、日本でも有名作家となっていたパウロ・コエーリョの小説の翻訳依頼が来た。訳書を出した経験があったことですぐに訳者に決定し、『ブリーダ』(2009年)、『マクトゥーブ 賢者の教え』(2011年)、『不倫』(2016年)、『ザ・スパイ』(2018年)と、コエーリョ作品の訳をそれから続けて手がけることになった。
持ち込みの秘訣は
「熱」を伝えること
出版翻訳の仕事が定期的に入るようになってうれしかったが、デビュー作の著者も、コエーリョもブラジルの作家。ポルトガルにもおもしろい作品はある、いつかはこれらを日本に紹介できたら…という新たな目標ができた。
また、ずっと独学で翻訳を続けてきていたが、2014年に翻訳家の鴻巣友季子氏が主催した出版翻訳者が集まるFacebookグループに参加して、はじめて同業者の知人ができ、勉強会などにも参加するようになった。
「グループの方に教えてもらって、鴻巣先生の大学での講義に聴講生として参加し、色々な翻訳講座にも通うようになりました。それまで、ポルトガル語の文芸翻訳なんて学べる場所は無いとあきらめていましたが、翻訳者の方と交流したり、講義を聞いたりして、英語の翻訳から学べることが多くあると気づきました」
この頃までに、翻訳出版企画を持ち込んだこともあったが、最初の3本は企画が通らなかった。だが、特に好きな作家であるジョゼ・ルイス・ペイショットの『ガルヴェイアスの犬』はどうしても出版を実現させたかった。どこへ持ち込めば良いか悩んでいたところ、鴻巣氏が企画書を見ようと声を掛けてくれ、「これはいける」と太鼓判を押された。鴻巣氏から新潮社クレストブックスの編集者を紹介され、結果、翻訳出版が決定した。

「本当に思い入れのある作品で、作者のペイショットさんには日本で講演会があったときにお会いして、『あなたの作品の翻訳をしたい』と伝えていたので、実現して夢のような気持ちでした。さらに日本翻訳大賞を受賞したことで、ポルトガルの文学を多くの人が知ってくれたこともうれしかったです」
その後も木下さんは、アグアルーザ『忘却についての一般論』(2020年)、タヴァレス『エルサレム』(2021年)と、持ち込みから翻訳出版を次々と実現させた。2023年以降に出版予定の企画も3つほど動いている。持ち込みを成功させるコツは、なんといっても熱意がこもった企画書だそうだ。
「企画書では読んで感じた『熱』を伝えることを重視しています。どこがおもしろいのか、読みどころなのか、魅力をわかりやすく書く。例えば『ガルヴェイアス』では、『オフビートな黙示録』、『ポルトガル版楢山節考』といったキャッチーな売り文句も盛り込みました」
企画書を書くスキルは意外なところで磨かれた。大使館を退職した後に、生活クラブの書籍購入カタログの選書委員を6年間つとめ、そこで本の紹介文を書いていたことが、人に読まれることを意識した文章の鍛錬になったという。
翻訳大賞の受賞もあって注目が集まり、ポルトガル文学が毎年出版される、という環境に嬉しさを感じる一方で、後進を育てていかなければという思いもある。
「たった数人ではとてもその国の作品をカバーできませんから、訳者はもっと出てきて欲しい。2021年から、大使館で年1回、ポルトガル語の文芸翻訳ワークショップを始めました。実力のある人が集まり、私自身とても勉強になっています。今後この中から、翻訳者としてデビューする方が出てきたらうれしいです」


Advice! 「その他の言語」の出版翻訳をめざす人へ
翻訳出版企画の持ち込みは緊張しますが、マイナー言語の作品は編集者の方も情報を追い切れていないので、決まるかは別にしても、書籍の情報自体はありがたがってくれることが多いです。英語などとは違い、翻訳者が自分で動かないと企画は生まれないので、特に「その他の言語」で活躍する方たちは、ぜひ思い切って持ち込みをしてみてほしいと思います。
また、海外と日本では同時代でも売れる本が異なります。そのときは日本での出版が難しい作品でも、数年後には読まれる土壌ができている、ということも。これはと思う作品があれば、あきらめずに機を待ってみて下さい。
木下眞穂さんのリレーエッセイはこちら!
→「マイナー言語」だからこそ生まれたポルトガル語の仕事の縁
※ 『通訳翻訳ジャーナル』2023年冬号より転載。