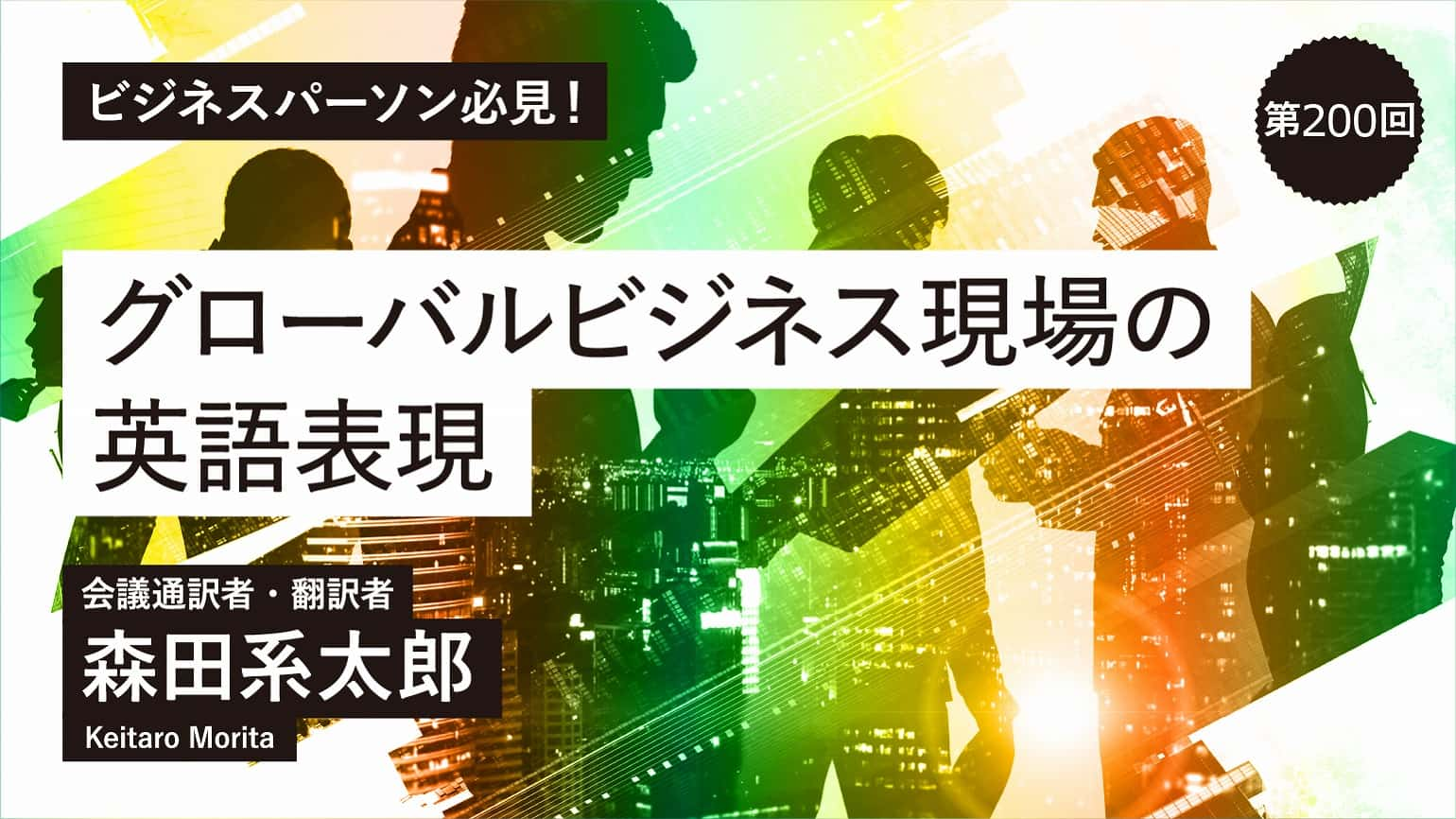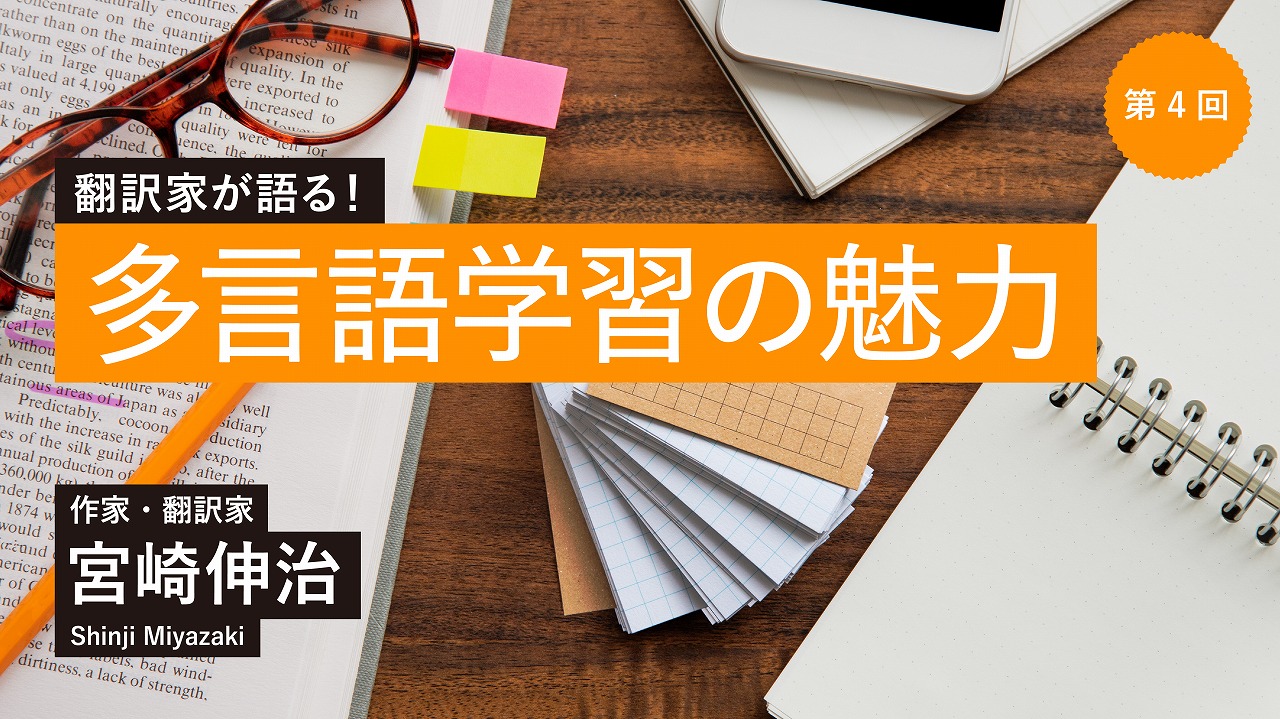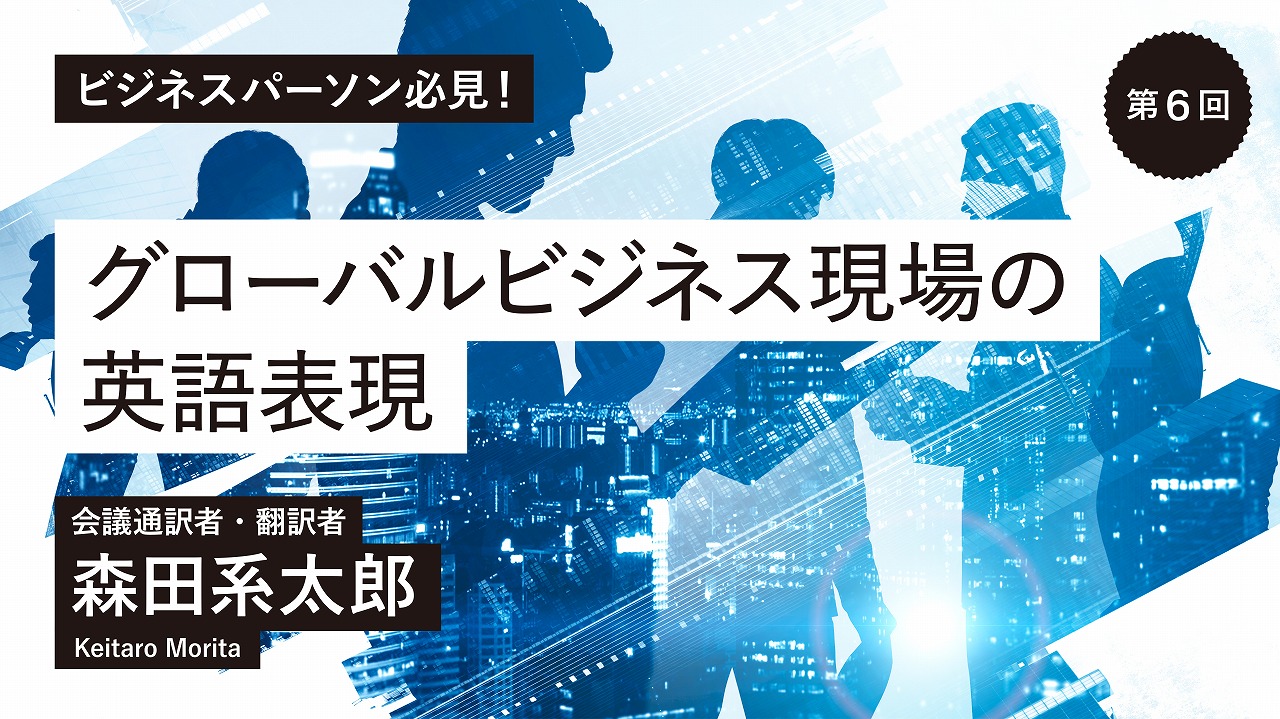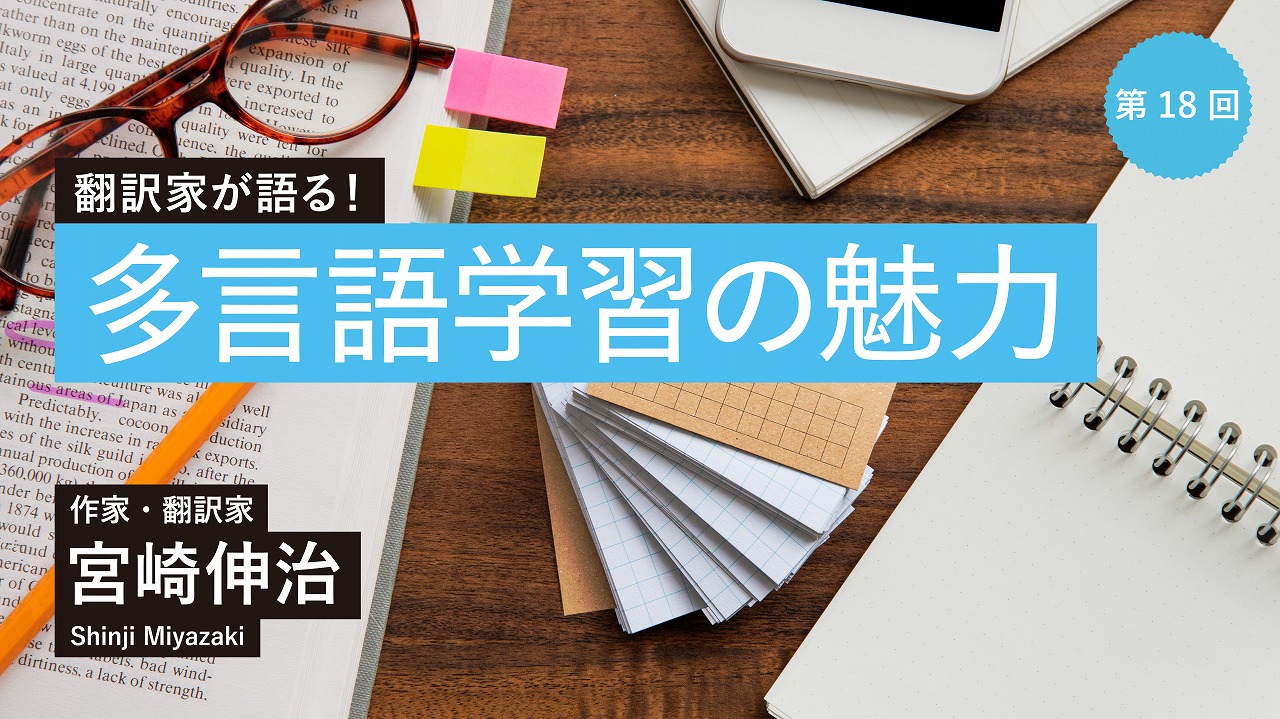会議通訳者、兼、スポーツ通訳者として活躍されている、平井美樹さんによる連載コラム!
日本スケート連盟の通訳者として数多くのフィギュアスケートの大会で通訳を務めるほか、五輪やサッカーW杯、ラグビーW杯にも通訳として関わる平井さんが、フィギュアをはじめとするスポーツの通訳の仕事について語ります。
(※隔月更新予定)
通訳者に求められる「通訳」以外の役割とは
一般的な通訳とは異なるスポーツの現場
最近、自分にとっては新しい競技の案件を担当したのですが、どの競技も似たような課題に直面しているのだなと痛感しました。
マーケティングをして観客数や収入を増やすため、国際競技団体レベルで新たな試みがなされています。一番心配なのは選手たちに負担にならずにそれができるかだと思います。こういった改革の波を受けて、多くの競技で活発な議論が展開されています。
国際的な会議の場で、日本の競技団体もどんどん発言をしてプレゼンスを高めてほしいなと思いました。今回、私は通訳をするだけではなく、代弁者として参加し、文書の作成などいろいろな役割を担いました。これは通訳者の仕事の域を超えていますが、私はそれを織り込み済みでお引き受けしました。
馴染みのない競技のため色々と教わりながら、国際交渉の力学については、私なりの解釈も含めてアドバイスをさせていただいています。競技経験がないことをお客様(クライアント)もご存知の上で、それでも通訳プラスアルファの部分を評価していただき、ご依頼をいただきました。
ちょうど、こういった通常とは違う業務をお引き受けしているタイミングで、水原一平氏の判決が出ました。
彼のおかげでスポーツ通訳者に光が当たったことも確かです。しかし、スポーツ通訳というジャンルが確立されていないがゆえの闇も露呈しました。チーム、監督、競技団体などの通訳を務めるときには、いわゆる通訳業界でいう一般的な“通訳者”という定義が通用しないことが多々あります。“英語のできるスタッフ”、“通訳もできるスタッフ”、“英語と競技がわかる何でも屋”から“交渉人”まで。通訳以外にも多くの役割を担う場合があります。
FOX 11 Los Angeles:An unscrupulous person takes advantage of the trust place in them to victimize a vulnerable individual.
(水原被告の刑確定について当局の記者会見 2025/02/07)
そういった多くの役割をこなす通訳の仕事では、交代要員がおらず、1人でずっとウィスパリングすることもあるかもしれません。メモを取らずに通訳をすることもあるでしょう。監督や選手のご家族のお世話や病院への付き添い、身の回りのお世話から、海外からお友達が訪問した際のお世話まで行います。今回の私のように、会議に同席して代弁をするということもあります。賃金レベルも多種多様。それでもそのスポーツが好きだから、貢献したいから仕事を受けているという方々が多いはずです。
業務範囲や対価については適切に交渉を
一方、会議通訳などの世界では、「通訳」以外のことはなるべくしない、というプロフェッショナル職としての掟があります。もちろん、社会人としての常識範囲内で、多少のお手伝いなどはしますが。
AIの通訳・翻訳能力が高まっていくこれからの時代、通訳者の定義もスポーツの分野における通訳者像もますます多様化すると思います。選手の気持ちを、直訳ではないけれどもしっくりとくる表現でまとめ上げ、メディアが使いやすいような訳出をする。そこに付加価値も生まれるかもしれません。ただ、通訳者としての基本、つまりは話者の発言をきちんと理解、解釈して、違う言語に訳出する能力の重要性を肝に銘じていかないと痛い目に遭うと思います。
話者と通訳者がお互いに慣れ親しむと、良い化学反応を生むこともたくさんありますが、話者との距離感が近くなると、自分がその人になったかのような錯覚を起こすことはあります。スポーツチームの監督の通訳者になると、よく、選手もスタッフも通訳者の言葉=監督の言葉、という錯覚に陥りやすくなります。プロ意識のある通訳者は必ずそこを切り離しています。話者の熱意を伝えるために熱い通訳をしても、自分がその人になったような万能感や勘違いは御法度です。そこを見失わずに求められている役割をこなせる人こそプロフェッショナルです。
通訳者を雇って利用する側には、それに見合った適切な対価を払う、業務範囲や役割を明示することが求められます。スポーツ通訳者は、どこまでの業務を受け入れて、それに対する自分のサービスの価値を交渉できる姿勢が必要だと思います。スポーツ関連のお仕事はエージェント経由ではなく直接のやり取りになることが多いため、交渉も自分で行う必要があり、そこが難しいのですが、自分のプロとしての価格は常に意識していたいものですね。これもプロのアスリートから学んだ大切なことです。
スポーツの世界は職人の世界と同じで、アスリートだけではなく彼らを支えるあらゆるプロフェッショナルが揃っています。スポーツ通訳者としてのプロフェッショナリズムを私たちひとりひとりが持たないといけませんね。
★前回(第10回)の記事はこちら
★連載一覧はこちら

会議通訳者兼スポーツ通訳者、 日本スケート連盟通訳者。学生時代にESPN Sports Centerを翻訳するアルバイトから通訳の道に入る。NHKの大リーグ、NBA、NFL放送の通訳スタッフ、広告代理店の社内通訳を経て、現在はニュース、国際関係、安全保障、企業買収からエンタメ、相撲の英語放送までをこなす放送・会議通訳者。五輪やサッカーW杯、ラグビーW杯にも通訳として関わるほか、日本スケート連盟の通訳者でもあり、数多くのフィギュアスケートの大会で通訳を務める。日本から海外へのPR、エグゼキュティブ向けグローバルコミュニケーションコンサルタント、企業からアスリートまでのメディアトレーニングも手がける。