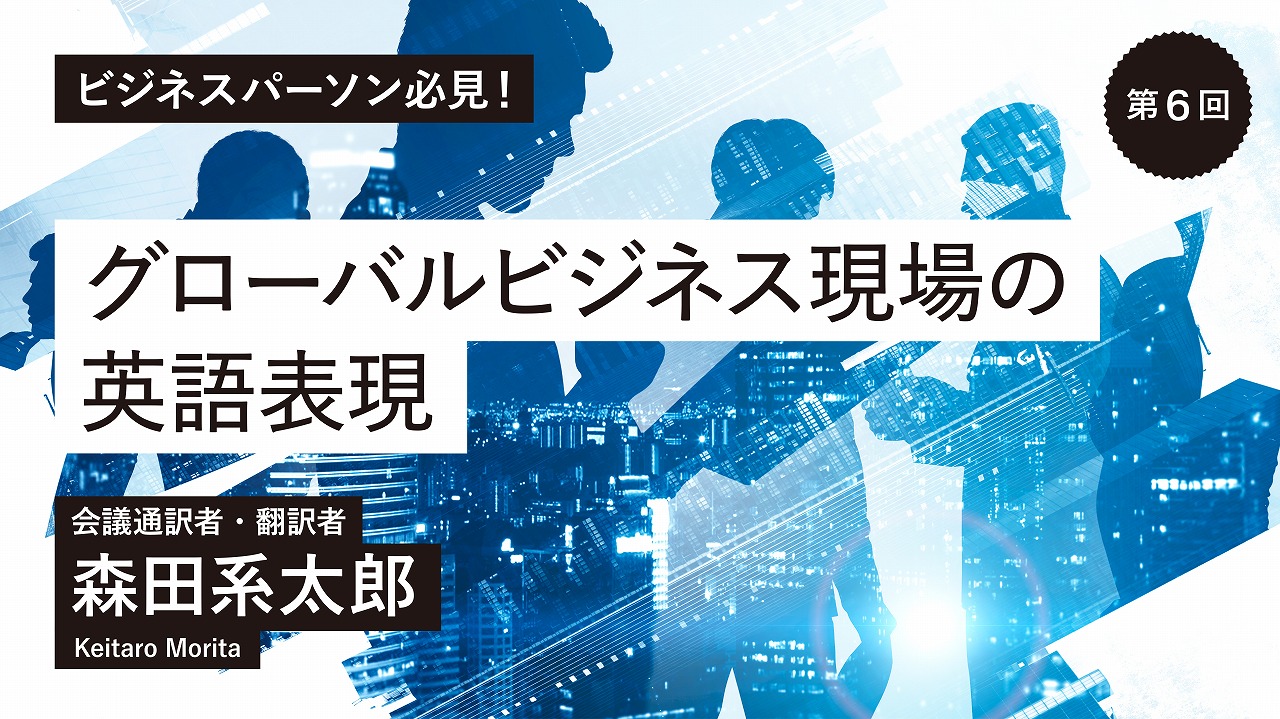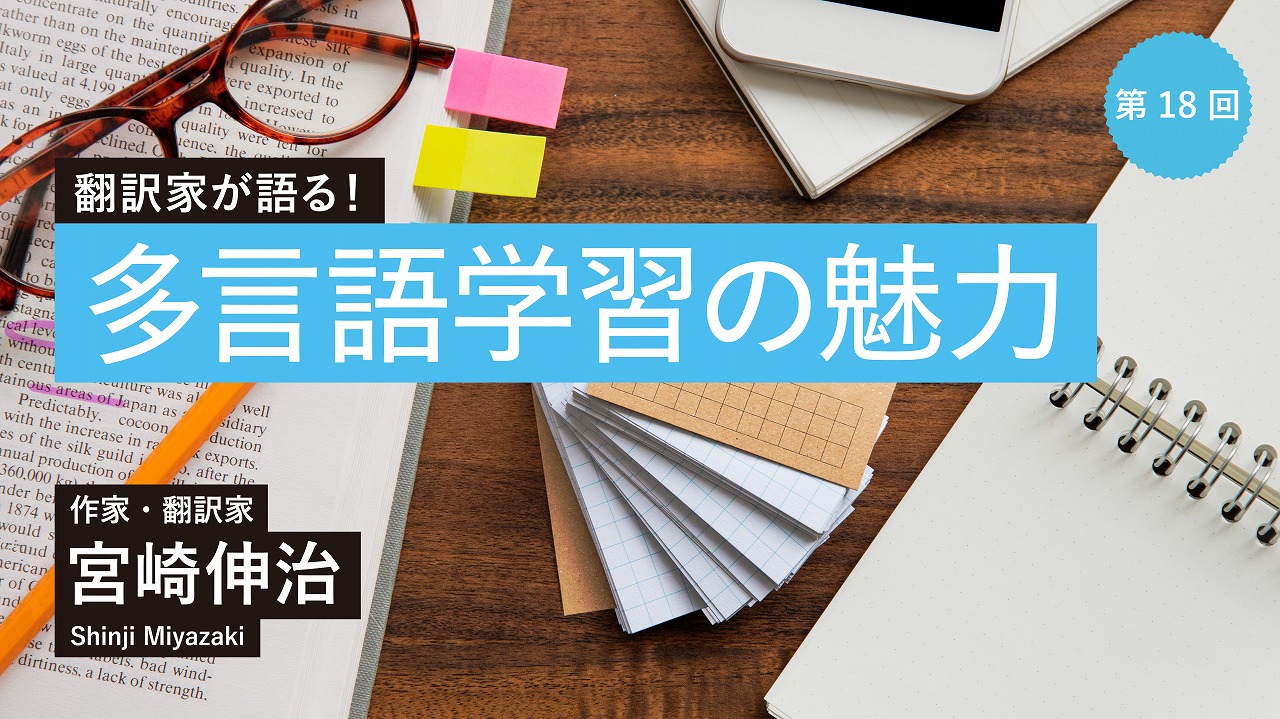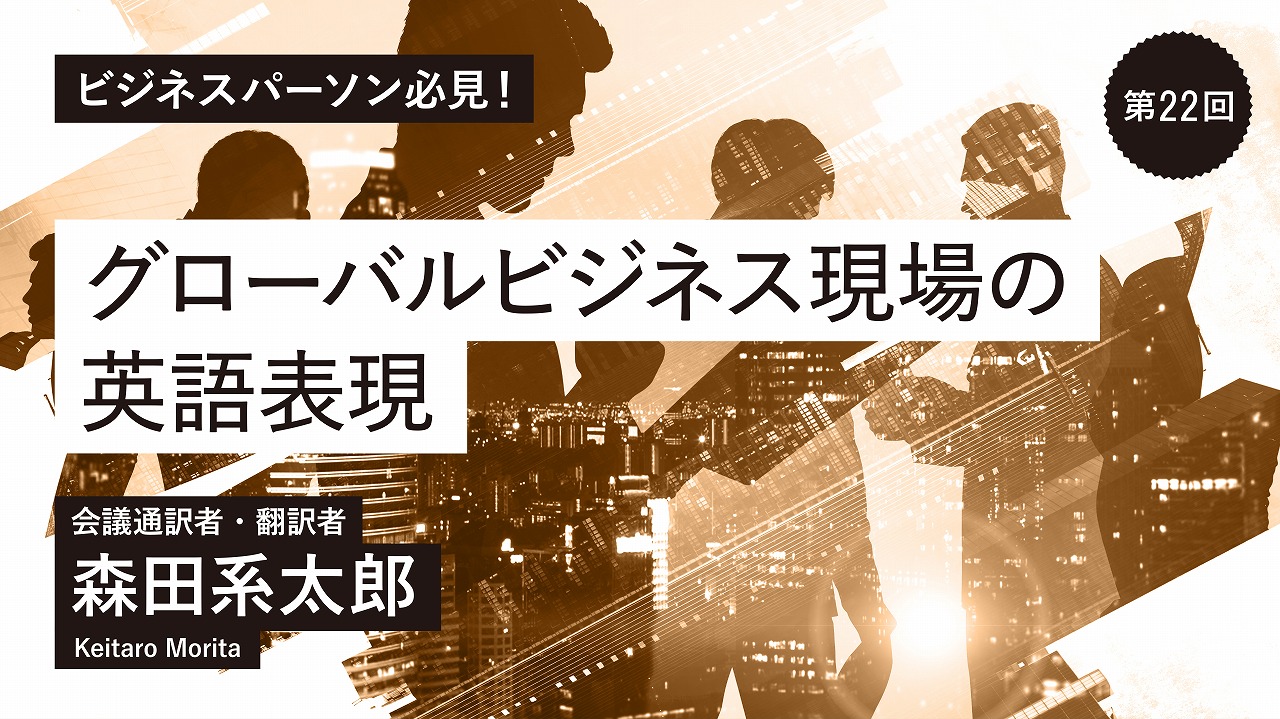通訳業界に関わって30年以上で、現在は一般社団法人 通訳品質評議会 理事 を務める藤井ゆき子さんが通訳者のキャリア形成について解説します。
どんな人が通訳者に向いているのか
今までの経験で、中学校や高校から職場見学の依頼を受けて対応をしたり、また高校への職業紹介への出前授業をしたり、さらに通訳を科目として教えている大学でのセミナーの依頼でうかがうことがありました。現場でよく聞かれたことは、「どうやったら通訳になれるの?」「どんな人が通訳に向いているの?」の2点です。
今回は「どんな人が通訳に向いているの?」について、今までの業界経験のなかで私の考えをご説明したいと思います。
知的好奇心が旺盛な人
どんな人が通訳に向いているかという点については私の考えをまとめてみたいと思います。
まず、「知的好奇心が旺盛」な人。ベテランになると分野を絞る方もいますが、最初は分野を選んでいられません。特にフリーランスになったら、実績を積むために毎日違う仕事をするケースが多いです。
月曜日はメタバースweb3の研究会で、火曜日はIoT家電の商品発表会、水曜日はメーカーの取締役会、木曜日はスポーツイベントのインタビュー、土日は医学の会議……なんてこともありえます。
毎日毎日違う分野の内容を準備し、勉強していかなくてはなりません。大学等の専攻とは関係なく、現場のニーズに応じて基礎から勉強しなくてはならない分野もあるでしょう。その勉強をすることで、いままで知らなかったことがわかっておもしろい!と思えるタイプの人と、受験勉強のように仕方なくやるタイプの人とを比べれば、前者のほうが仕事のストレスは低くなるので向いています。
さらに昨今のオンライン会議の増加に伴い、I Tリテラシーが求められてきましたので、これも新たなチャレンジです。色々なプラットフォームがありそれを苦痛と思うか好奇心を持ってトライするかは、これから成長できるかどうかの分水嶺になるかもしれません。
体力やストレス耐性
次は「体力」や「ストレス耐性の強さ」です。
先程の事例からわかるように、毎日違う分野の勉強をする体力が必要です。コロナ後は出張も増えてくると思われますので、出張に耐えうる体力がいります。
そして毎日違う場所、違うクライアントや聴衆、違うパートナーと仕事をする環境ですので、それに対応できるストレス耐性が求められます。特にフリーランスの最初のころは毎日「初めまして」の環境ですので、普通のサラリーマンでも新しい職場の最初の日はグッタリ疲れると思いますが、それがほぼ毎日ということを想定していただければわかると思います。
地道な努力ができる意思の強さ
ここでいつになったら「留学」の話や「帰国子女」の話がでてくるのかしらと思う方がいるかもしれません。確かに、通訳者として就業している方の中で留学経験者、帰国子女率は高いです。雑誌や新聞社から留学経験がなく、帰国子女でない方にインタビューさせてほしいという依頼に対して、いざ探すと結構少ない状況でした。
もちろん外国語の語学力が高いことは有利ですが、日本で通訳をする場合はクライアントには日本人が多いので、やはり日本語の能力が評価されます。日本語の豊富な語彙と表現力は強い武器になります。また話者の意図を把握する力が何よりも重要で、ネイティブ並みの発音がいくらできても、単なる言葉の置き換えでは意図を正しく伝えることはできません。
日本語と外国語のセンスを磨き、話者の意図を把握して正確にメッセージを伝えるのは簡単に習得できることではありません。アスリートと同じで、常に自分の成長をめざして「地道なスキルトレーニングに努力し続けられる意思が強い」ことが3番目の適性と言えるでしょう。
大切なのは通訳者をめざす理由
さらに能力や適性以上に本当に大切なことは「なぜ通訳になりたいのか」という理由、大げさにいうと“志”があるかどうかだと思います。これはどんな仕事にも言えますが、めざす理由があるとないとでは、成長も達成感もまったく異なるでしょう。
単に語学が好きだから、得意だから生かしたいだけでは、この厳しい通訳という仕事は続きません。今まで若くしてスキルの高い方が、早期にあっさりリタイアする例をいくつか見てきました。本人達にインタビューして答えを引き出した訳ではないので、あくまで私の推論ですが、簡単に習得できた人にとっては手放すのも惜しくないのかもしれません。またサービス業という側面からやりたい仕事ではなかったのかもしれません。または通訳という仕事が自己実現の場として魅力がそれほどその方にはなかったのかもしれません。
どんな仕事でも、仕事に就く前に既にそれなりの志のある方もいれば、仕事を始めてから自分で気づく方もいると思います。仕事を続けるうちに見えてくることでも良いと思います。
私の大学卒業時は就職氷河期で、選択肢などない時代でしたが、時代によっても異なります。現在は労働人口減少から人材不足が課題としてマスコミでも取り上げられ、逆に売り手市場ですね。だからこそ「なぜこの仕事をしたいのか、その仕事で何を成し遂げたいのか」をぜひ考えてほしいと思います。
次回はライフステージに応じた仕事の仕方について書きたいと思います。

慶應義塾大学卒業後、日本外国語専門学校(旧通訳ガイド養成所)に入職。広報室長を経て、1987 年(株)サイマル・インターナショナルに入社、通訳コーディネーターとして勤務後事業部長を経て2012年11 月に代表取締役就任。2017 年4 月末に退任後、業界30 年の経験を生かしフリーランスでコミニュケーションサービスのアドバイザーとして活動。2017 年10 月より一般社団法人通訳品質評議会(https://www.interpreter-qc.org)理事に就任。
おすすめの記事
-
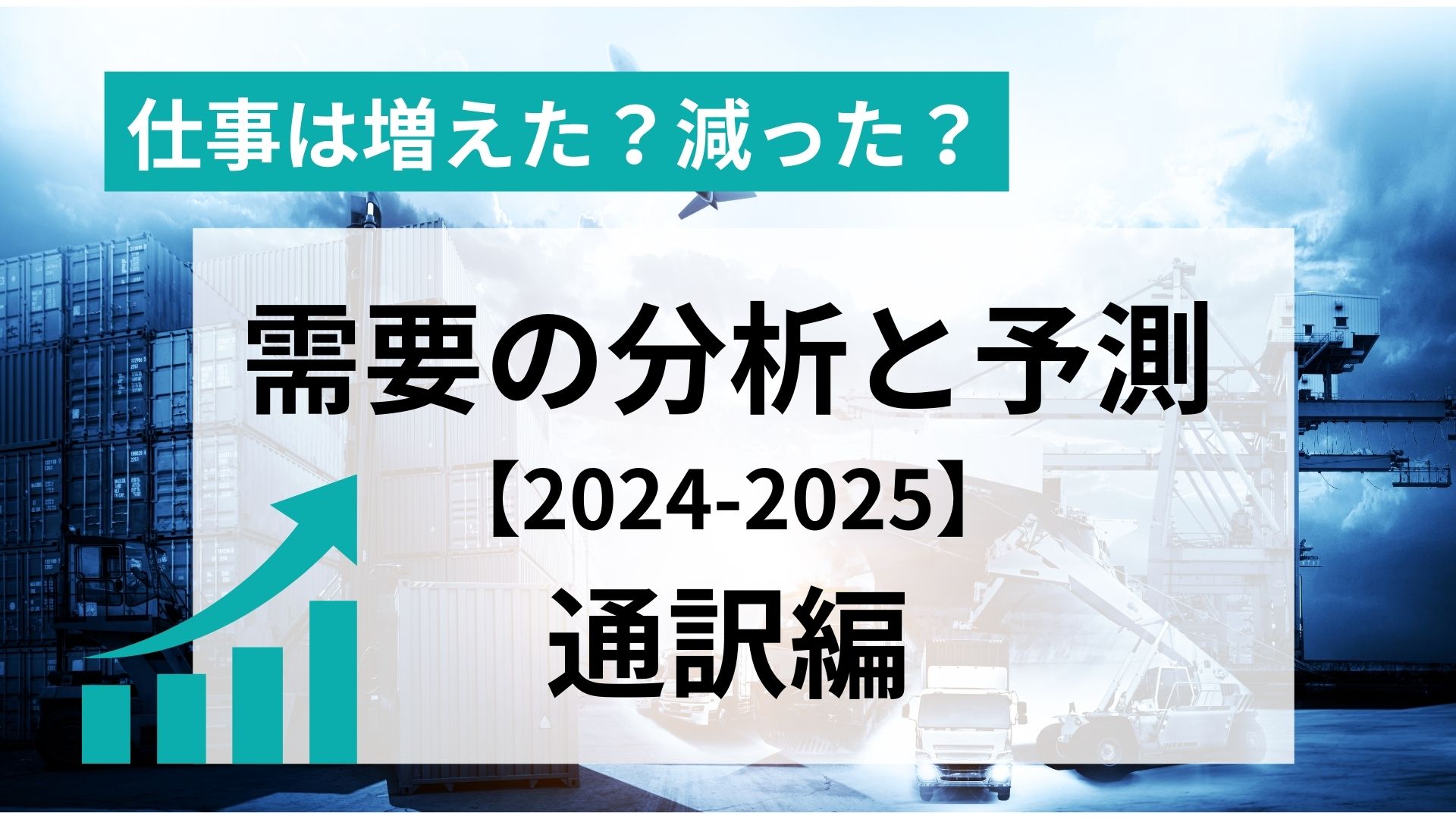
2025.03.07 UP
通訳の仕事は増えた? 減った?
需要分析と予測【2024-2025】―通訳編- #キャリアアップ
- #営業・仕事獲得
-

2025.02.25 UP
通訳会社・翻訳会社で働こう! 職種や仕事内容を紹介【求人情報あり】
- #人材募集
- #キャリアアップ
- #営業・仕事獲得
-
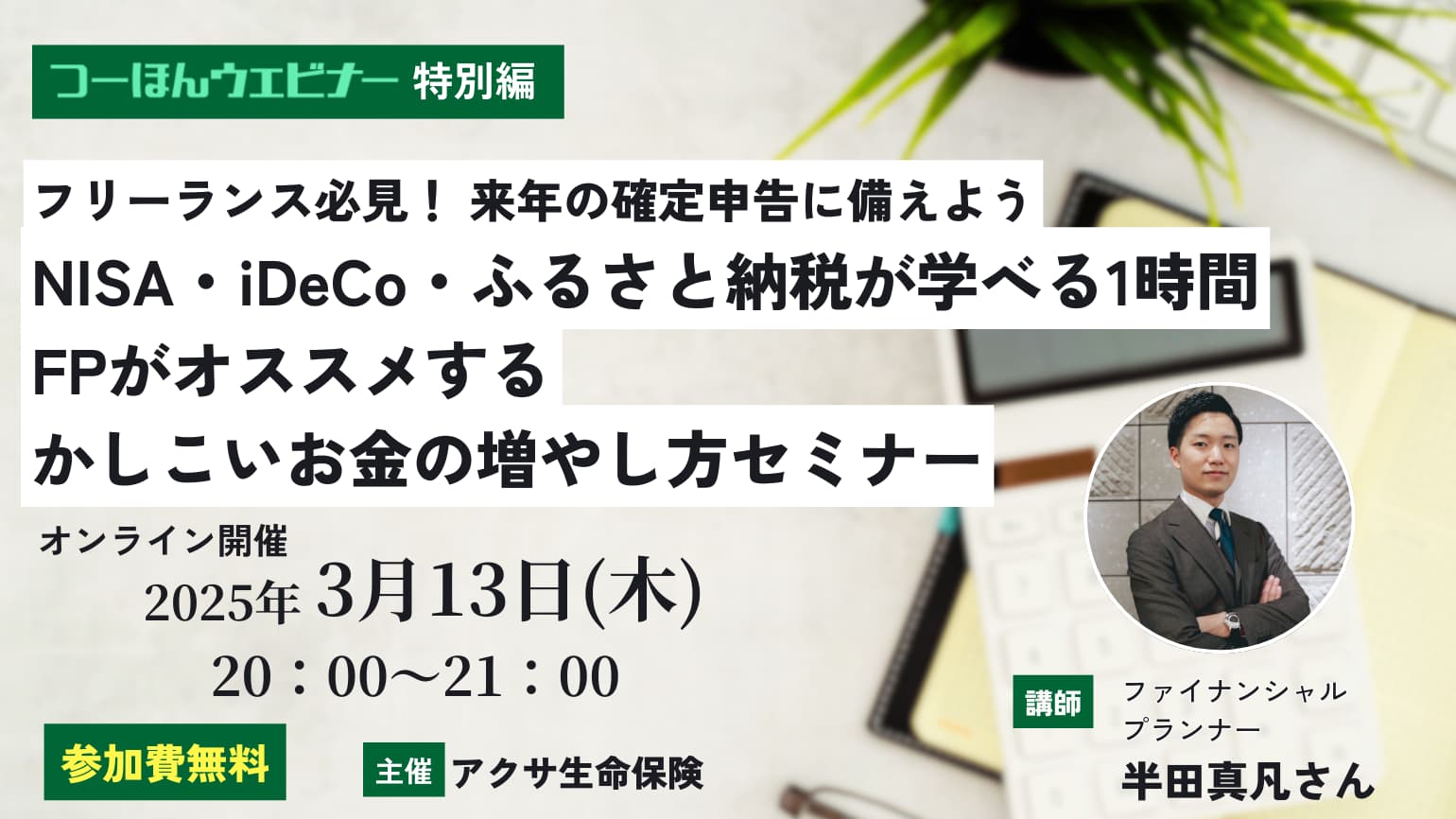
2025.02.21 UP
【つーほんウェビナー特別編】フリーランス必見! 来年の確定申告に備えよう
NISA・iDeCo・ふるさと納税が学べる1時間 FPがオススメするかしこいお金の増やし方セミナー- #ウェビナー&イベント
- #キャリアアップ
- #事務・税務・法務
-
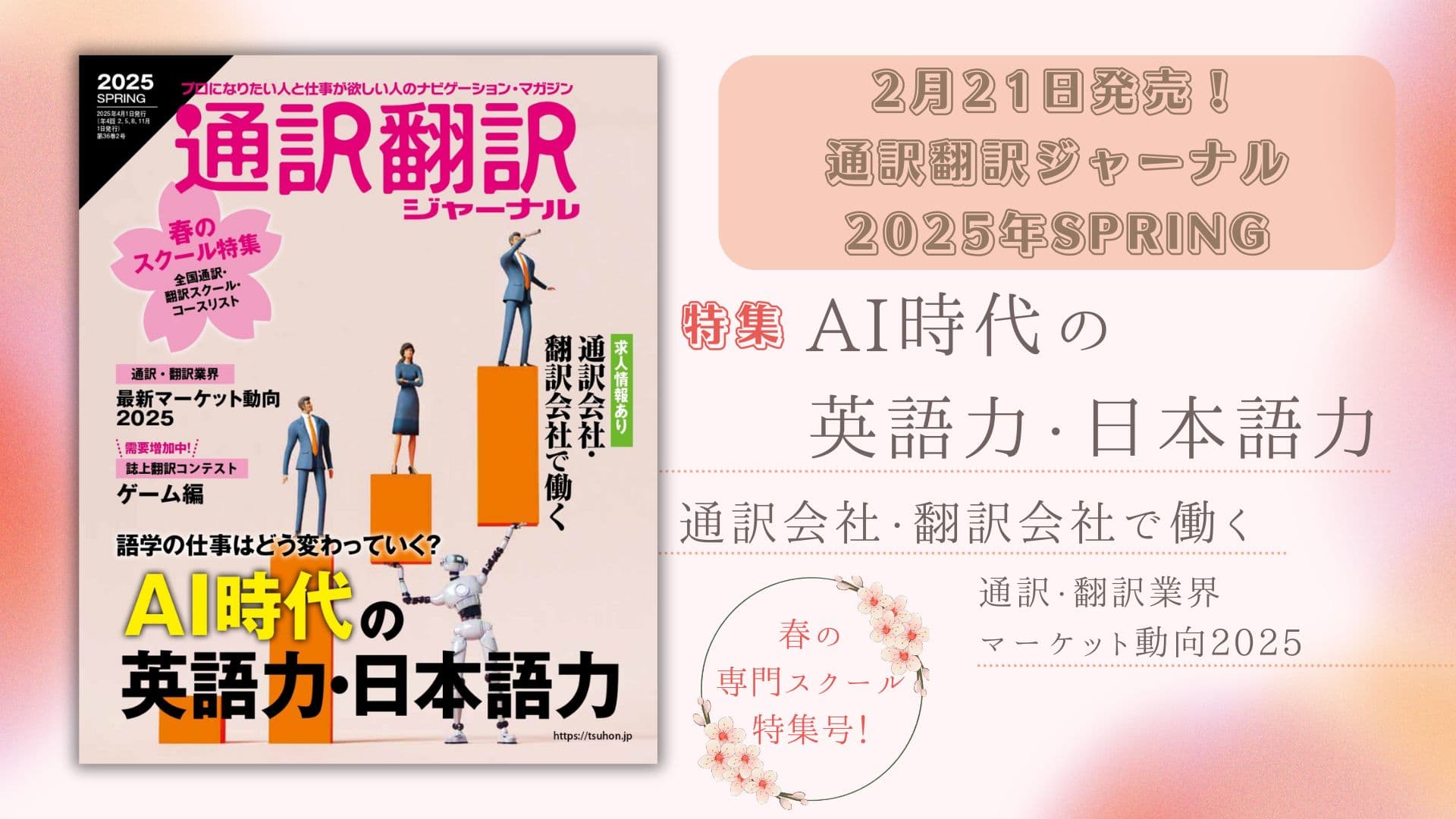
2025.02.21 UP
通訳翻訳ジャーナル2025年SPRING 2月21日発売!
- #キャリアアップ
- #仕事に役立つ本